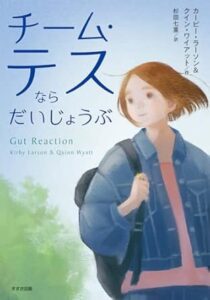 |
出 版 社: 鈴木出版 著 者: カービー・ラーソン, クイン・ワイアット 翻 訳 者: 杉田七重 発 行 年: 2025年06月 |
< チーム・テスならだいじょうぶ 紹介と感想>
通勤通学途中に急激にお腹の具合が悪くなってトイレを探す。誰にでもあることかと思いますが、その頻度によっては、日常生活に支障が生じます。便意はなかなかコントロールできないものです。授業や仕事など途中で抜けだすことができない状況だったり、試験中にそうなってしまったらと思うと、恐怖心さえ抱いてしまいます。心因的なものが原因のこともあるので、心配すればするほどリスクが高まるような気もします。通勤や通学が電車なら途中下車すれば駅にトイレがありますが、バスはかなりリスキーですよね(自分もそうですが、この傾向のある人は、自分の生活圏のどこに入りやすいトイレがあるかは把握しているものと思います)。本書の主人公は、そうした深刻なお腹の事情を抱えており、多かれ少なかれ、こうした傾向がある人にとって共感をもって読むことができる物語です。とりわけ「多かれ」の人にとっては切実な話であり、それが特定の腸の病気となると、より関心を持たれるかもしれません。実際、お腹がゆるい、というのは、なんとなく気恥ずかしさもあって、人に言うことも、病院で相談することもはばかられるものです。思春期にとってはより恥ずかしいものであろうし、我慢して嵐が行きすぎるのを待って、やり過ごすしかないものでしょう。実際、なんらかの病的と思われる症状があっても、自分が病気だとは認めたくないものです。それでも治療をしなければ、改善することはないのです。診断を受けることにさえ高いハードルがありますが、まずはそこを越えなくてはなりません。結果的に治療法の確立していない腸の難病に罹患しているという事実に主人公は直面します。お腹の具合の悪さに苦しめられるのを軽減するには、腸を刺激するような食べ物を避けるしかない。ここからが正念場です。治療法のない病気と向き合い、生涯、付き合っていくこと。そんなハードな人生を生きる覚悟を持つ。それには、支えてくれるチームの存在が重要なのです。
ノースレイク中学に転校してきた二年生のテス。今までの学校よりもずっと大きいこの場所に馴染めるのか不安に思っています。どうやって友だちを作るか。すでにグループができあがっているところに、加わるのは難しいものです。以前なら友だちと過ごしていた放課後も今は一人。ここに引っ越しをすることが決まってから、どうもお腹の具合が悪くなりがちなこともテスを悩ませています。キツツキがお腹を突っつくような痛み。これにいつ襲われるかわからないのです。胃腸の不調と、早く友だちを作らなくてはならないというプレッシャーにテスは落ち着きません。色々なグループに近づきながら自分の居場所を探すテス。ひとり寂しくランチを食べる日々からなんとか抜け出したかったのです。ようやくエリーとラジットという友だちを得たテスでしたが、お腹の不調は変わらず、テスを悩ませます。それでもエリーとは三年前に心臓発作で亡くなったパパのことも話せる深い友だちになっていきます。そしてエリーに背中を押されて、テスの趣味であるお菓子づくりのコンテスト番組「ベイクオフ」への参加申し込みを決意します。出場を目指して、エリーやララジットと作を練る楽しい日々の傍ら、テスの胃腸の不調は続き、突然、深刻なピンチに襲われようになります。やがてこの症状が、クローン病という慢性疾患であることが判明します。根源的な治療法はなく、ずっと付き合っていかなければならない病気です。それでもベイクオフへの出場も決まったテスは覚悟を決めます。今は、自分を支えてくれる友人たちがいます。治療をしながら、コンディションを整え、アイデアも練る。来るべきベイクオフ本選で、不調を抱えながらもテスはその実力を発揮できるのか。友人たち、チーム・テスのサポートを受け、テスは決戦へと臨みます。
お腹のコンディションの悪さについて、気軽に共有できるのは家族だけだろうと思います。腰が痛いとか、膝が痛いとかのように気軽に口にすることが、なんとなくできない。その心理的抵抗は恥ずかしさであり、それを越えるのは、どこまで信頼関係があるかでしょう。信頼関係って、どうやって築くものだったか、とあらためて考えます。転校生であり、友だち作りが得意というわけでもないテスは、手探りで友人を見つけていきます。このプロセスも共感をもたらすところかと思います。自分の便意や腸内事情について打ち明けられるまでの友人を得るのは至難の業であって、友だちを探すところから考えはじめると、ちょっと気が遠くなるところです。エリーとラジットと親しくなっていき、三人でベイクオフ参加のための動画を撮影するあたりなど、友だちと親密になっていく蜜月を莞爾として見守ってしまう良い場面です。人との関係構築は縁と運があります。そうした意味では、難病の友人を得た人たちもまた多くのドラマを体験することになるでしょう。知っている方がクローン病になって、あまりにも急激に痩せていき、その外見の変化に驚かされたことがあります(おそらくは病名を公表しないと周囲も対応が難しかったのではないかと思います)。闘病しながらも仕事生活を送られている、その内面の葛藤は知るところではなかったのですが、同じ職場のごく身近な方たちもまた、どうサポートするか悩まれたかと思います(そうした良心的な職場であれかしですが)。人を支えるには、自分がしっかりと立っていなければならないものです。「介護疲れ」は確実にあります。さて、ここで介護という言葉を使う良し悪しがあります。介護には、やや義務的なニュアンスがあり、そう好意的に受け止めらる表現ではないでしょう。では、介護ではないサポートとはなんぞや。介護ボランティアではないサポートチームとはなにか。この支え合う人と人との結びつきについて考えさせられる『チーム・テスなら大丈夫』という邦題です。チームが「組織」になってしまうとまたズレていくので、この有機的なチームの程よい繋がりについて考えさせられます。チームガバナンスなんて考えなくていいチームに入りたいものです。さて、本書のもうひとつのキーワードが「ベイクオフ」です。自分もよく『ブリティッシュベイクオフ』をテレビで視聴していますが、素人がお菓子作りの技を競い合うだけではないサムシングが魅力です。コンテストで勝負しながらも個性的な参加者たちが互いにそれぞれをリスペクトし、また困難に挑むことで連帯していく、そんなチームになっていくあたりが見どころなのです。最終決戦前に、ここまでに脱落した参加者が集まり、勝ち残った人たちを賛辞し、応援するのも良いところ。人と関わるのは億劫なものです。そんな心情を前提として、組織に積極的に参画しようというタイプではない個が強い人たちが、いつの間にかチームになるからこそ生まれる感動があるなと思うのです。同情や綺麗ごとではなく「連帯」するチームに感慨を覚える本書の魅力を満喫ください。ところで、本書もそうなのですが、章の終わりにお菓子のレシピが載せられているYA作品がいくつかあったことを思い出しました。『みんなワッフルにのせて』や『負けないパティシエガール』もそうだったか。ちょっとしたデザート的なインサートが楽しいものです。