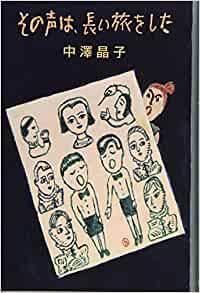 |
出 版 社: 国土社 著 者: 中澤晶子 発 行 年: 2019年10月 |
< その声は、長い旅をした 紹介と感想>
記憶なんてあいまいなものです。ちゃんと記録しておかないと正確な形で人に伝えることはできないだろうと思います。この物語には江戸時代に迫害されたキリシタンたちが、聖歌を文字に残さないまま耳で聞き覚え歌い継いでいったというエピソードが語られています。口承で伝えられた歌は、ラテン語の歌詞も原型を留めていないのですが、数百年を経て現代にその歌が届いたという、このロマンは壮大で、ちょっと感動的です。それを人が為したことも神の恩寵だと換言してしまうと、信仰のない人間としては感動の焦点がぼやけるのですが、多くの人生がひとつの歌をパスしながら、未来へと送っていったという事実は、やはり貴く、感じ入ります。ともかくも、魅力的な要素に溢れた物語です。合理的な説明がつくわけではない不思議な現象が描かれた物語でもありますが、それぞれの要素が輻輳して織りなされるとき、どこか腑に落ちてしまうことも興味深いところです。現代の少年合唱隊の子どもたちが、美しい声を持った子に抱くライバル心は、どこか憧憬にも似たものがあり、しかもその美しい声の命は変声期までという儚さをあらかじめ持っている、というのも常套ですが床しいものです。そんな寸景と、かつてヨーロッパに派遣された天正遣欧使節の影の一員だった少年の人生がリンクし、数百年の時を越える悠久のロマンが花開きます。国内の児童文学作品としては、久しく見ない雄大で繊細な稀有な感覚を紡ぎ出すこの筆致に、是非、酔わされて欲しいところです。『光草(ストラリスコ)』のような海外作品が好きな方にもお薦めします。
四番町少年合唱団は、はじまりが教会の聖歌隊だったため、宗教曲やヨーロッパ中世・ルネサンスの音楽を主なレポートリーとしていました。全国十指に入るというこの合唱団には優れた歌い手が多く、藤枝開(かい)もそうした少年の一人でした。みんな仲は良いものの、互いをライバルとして意識しているハイレベルな仲間たち。そんな中に新しいメンバーとして入ってきたのが船原翔平です。声も耳もすばらしく、自分にはない絶対音感を持っている翔平に、開は天性の閃きを感じ、自分への失意を覚えるほどでした。歌に行き詰った時、森の礼拝堂と呼ばれている廃墟で声の響きをたしかめるという先輩の言葉を思い出した開は、一人、そこを訪ねることにします。果たして、そこにはすでに翔平がいて、歌を唄っていました。その声に耳をすました開には、翔平しかいないのに、ひとつの声ではなく、ふたつの声が重なったように聞こえました。翔平もまた、ここに誰かの気配を感じていました。誰もいなけれど、誰かいる。翔平のからだの底から響いてくる声は、「わたしの声を受け継ぐもの」を求める誰かのものだったのです。その不思議な声について秘密を共有した二人は、後日、謎を解こうと一緒に森に向かうものの、落雷で礼拝堂は燃え尽き、何も残されていなかったのです。さて、四番町合唱団は秋の定期演奏会で十六世紀の終わりにヨーロッパに派遣された天正遣欧使節の少年たちをテーマにして、その当時の歌を唄うことになりました。 その練習中、少年たちの歌声には、もうひとつの声が重ねられていきます。翔平はやがて、曾祖父が、さらにその祖先が四百年にわたり歌い継いできたという「歌オラショ」という歌が、グレゴリウス聖歌を原型にしたものだということを知ります。時の政府に聖歌を唄うことを禁じられ、何も記録を残せないまま口伝で歌い継いできた記憶。そして演奏会での開とのデュエットで突然の変声を迎えた翔平の危機を、その声は救ってくれます。この不思議が一体、なんなのか少年たちにはわからないままなのですが、その裏に並走する四百年前の物語を読者は知ることになり、その時間を越えた連関に胸を打たれることになるのです。
天正遣欧少年使節のサイドストーリーがここには語られていきます。かの有名な四人の少年たちのような高い身分の良家の子女ではなく、使節団に随行した身寄りのない貧しい従者の少年がもう一人の主人公です。その美しい声を日本に宣教にきた神父に嘱望されるものの、愛がなく人の心には響かないとも言われる少年の歌声。彼が使節の一行の一人としてヨーロッパに帯同し、身分の低さや教養のなさを蔑まれながらも、次第に、歌うことと人を愛することに目覚めていく物語です。時を越えて届けられたものは、一体、なんだったのか。その遺された思いが、現代で歌う何も知らない少年たちに作用していく構成の妙に唸らされます。プロローグの一行目から『およそ、この世の中に、変声直前の少年の声ほど美しいものはありません』という稲垣足穂のような耽美的なフレーズで始まる物語。こうして、ここにいて、ここにいないという謎の存在が語っていく「声の物語」がはじまります。この少年同士の距離感や関係性には、どこか不思議な結びつきを感じます。彼らが自分たちの「終わり」を意識しているあたりに、どこか普通の少年とは違う陰りがあって、そこに強く惹かれます。変声期を目前にした合唱団の少年たちにとっては一回、一回の演奏会が「最後」なのかも知れないという予感を孕んでいます。背がのびることは嬉しいものの、変声期が早まることを恐れている。ボーイソプラノとしての残された時間を、翔平はどう受け止めているのだろうかと考える開。少年同士のそんな感覚もまた魅力的な作品でした。