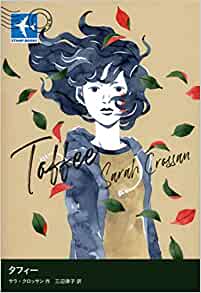 |
出 版 社: 岩波書店 著 者: サラ・クロッサン 翻 訳 者: 三辺律子 発 行 年: 2021年10月 |
< タフィー 紹介と感想>
昨今(この文章は2022年初旬に書いています)の国内児童文学作品には「モラハラ父さん、DV父さん」の登場が目立っています。そんな父さんを子どもたちがどう受け入れるかもまた主題になっています。本書を読むと、海外作品に描かれたDV父さんのレベルの違いに圧倒されます。やはりメジャーリーガー級です。無論、日本でもこのクラスのDV父さんが現実にはいるはずですが、児童文学では描きがたいのではないかと思うのです。酷いことをする父親にも自分なりの正しさがあります。それを躾と見做してしまうと、そこには愛があるのだと思ってしまう。いや、子どもは自分は愛されているのだと思いたいものです。この愛情を希求する気持ちに拘束されて、人はまんまと支配されることになってしまいます。拘束された心を解き放つにはどうしたら良いのか。物語に描かれていくのは、ノウハウではなく、虐待を受けた子どもが自分の心と向き合った軌跡です。そんな心の声が詩の形式(本も横書きです。『エレベーター』と一緒ですね)で綴られていくのが本書です。心境が詳しく説明されるわけでもなく、起きたことや状況も詩的に心象を表現したものであるため、分かりにくいと思います。ただ、そこには感じたことが感じたまま豊かに表現されているため、同調することができれば、より深く心に突き刺さるものとなります。結果的には、沈痛することになり、主人公にいたわしさを募らせることになる読書でした。ただ、そうした孤独な魂に寄り添うこともまた読書体験のもたらす得難いトリップなのだと思うのです。まあ、かなりしんどいです。
外出する際に娘の支度で待たされたことへの苛立ちで、ハサミで娘のポニーテールを切り落としてしまう父親。アリソンの父親は機嫌の良い時もありますが、その苛立ちから暴力に向かうことがあるのです。アリソンが飼っていた金魚をトイレに流してしまったり、長いシャツで隠していなければならないほどの青痣を彼女にいつも負わせてもいます。アリソンの心の支えだった同居していた父親の恋人のケリーアンもついには出て行ってしまいました。多くの痛みを抱えたアリソンは、顔に火傷の痕をつけたまま、これ以上の父親の暴力から逃れようと、町を彷徨い歩くことになります。16歳の少女には行く当てもなく、空き家と思った一軒の納屋に忍びこむと、そこにはマーラという老女がひとりで住んでいました。彼女は認知症を患っているらしく、アリソンのことを自分の子どもの頃の友人であるタフィーと混同し、受け入れます。とはいえ、マーラの認識は不安定で、アリソンをタフィーだと思うこともあれば、不審者のように見做したり、ハウスキーパーだと勘違いすることもあります。そんなマーラに話を合わせながら、ここで過ごしていくアリソン。彼女の心の中をずっと侵食しているのは父親との痛々しい記憶です。タクシー運転手の父親は、苛立ち、世の中を毒づき、気に入らないことがあれば不満をぶちまけ、家族に暴力を振います。そんな父親の顔色を伺い、機嫌をとろうとするアリソンは、父親に恐れを抱いているだけではなく、その愛情を深く希求しています。時折、父親が見せる優しさ。複雑な愛憎を父親に対して抱いているアリソンの心象が「詩的」に語られていきます。やがて父親に抱いている自分の本当の気持ちを打ち明けるという決意が育っていくプロセスも見出されます。メンタルが不安定なアリソンが、認知症で覚束ないマーラを支えていく、余りにも危なっかしい時間。途切れ途切れに吐き出されていくアリソンの心象から見える物語の進展を固唾を呑んで見守ることになる、実に緊張感あふれる作品です。
健常な人と同じようには、認知症の人と話をすることはできません。とはいえ、認知能力の衰えには波があって、全てが理解されないわけでもないのです。この付き合い方は非常に難しくて、受け流したり、言い聞かせたりしながら、なんとかコミュニケーションをはかるしかありません(自分もこれには経験があります)。端的には、話が通じないわけですが、人と人との関係性や情愛は、合理的なことだけでは説明がつかないものです。つまりは、話が通じることだけが人同士の繋がりではない。マーラがタフィーにかける言葉も、そもそもアリソンはタフィーではないのですが、それでも胸を打つ力を帯びていることは、理屈では説明できないものです。アリソンと父親の関係も、合理的な判断だけでは断罪できないのが厄介なところです。この人と人との繋がりは、理路整然と割り切って考えられないものであるために、人は悩み、苦悩するのです。愛情は理屈に合うものだけではない。国内児童文学作品の近年の潮流では、こうした家族の問題に、福祉や社会的制度を介入させていく傾向があります。苦しんでいる子どもを救う社会的手段を物語が明示してくれます。その一方で、正しさだけでは割り切れない愛憎も浮かび上がらせていきます。この物語では、そうした正しい解決策が見えないまま、アリソンは父親との訣別を意識します。そして、もうこれで終わりと思いながらも、ずっと心をかき乱され続けています。思えば、割り切れない気持ちがずっと描かれた物語でした。それでも、先に進んで行くのが人生です。父親は反省し、後悔することもなければ、マーラの認知症も良くなるわけではありません。それでも、アリソンは前を向いて、自分の道を歩いていくしかないのです。このエンディングはハッピーなのかだろうかと考えます。希望はある、と思います。父親を想い逡巡した時間やマーラとの触れ合いがもたらしたものがきっとある。この400ページの物語をアリソンと一緒に駆け抜けることで、説明できない感慨が得られると思います。説明できないことが、実にもどかしいのですが。