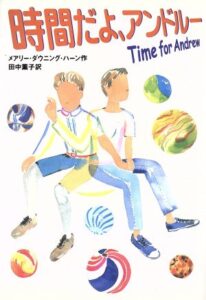 |
出 版 社: 徳間書店 著 者: メアリー・ダウニング・ハーン 翻 訳 者: 田中薫子 発 行 年: 2000年04月 |
< 時間だよアンドルー 紹介と感想>
この物語の起点は20世紀末(1990年代か80年代でしょう)。そこから20世紀初頭の1910年へと主人公はタイムスリップすることになります。20世紀の始まりと終わりでは、科学技術の進歩が著しいため、過去に戻った主人公は、その日常生活において不便を感じることになります。電話は壁掛けでダイヤルもついていない、冷蔵庫は氷を入れた木のアイスボックスです。自動車は発明されているものの、まだそれほど普及してはいません。もちろん、テレビもコンピュータもないのです。主人公のそうした驚きを見るのも読者としては楽しいところです。その20世紀初頭(1908年)に書かれた世界初のタイムトラベル児童文学である『アーデン城の宝物』と続編の『ディッキーの幸運』では、その当時の現代から300年前の時代に子どもたちがタイムスリップします。ただ、そこには科学的なギャップが少なく(カメラの存在などはありましたが)、それほど過去の時代に順応するのに抵抗が少ないようでした。1800年代初頭に書かれた『スイスのロビンソン』で、無人島生活を強いられた家族が野生生活に比較的順応が早いのも、当時の文化的生活とのギャップの少なさではないかと思います。ということで、時代が進み科学が発達して生活が便利になればなるほど、未開の時代や場所にいくことの抵抗が強くなるのです。タイムトラベルものの面白さは、未来視点で当時の風俗を驚きをもって知ることができるところです。それは科学技術の進歩だけではありません。そこには時代時代の考え方の違いも反映されており、子どもたちの気風だって違うのです。この物語では20世紀末の少年が、20世紀初頭の少年と出会い、入れ替わることになります。20世紀末の大人しい少年アンドリューと、20世紀初頭の悪ガキ、同名のアンドリューとでは、男の子とはどうあるべきか、という考え方のベースが違います。それぞれが、元いた時代とは別の時代に放り込まれた時、感じるのは、生活の便不便よりも、その考え方の違いでしょう。SF的タイムトラベルものとはまた一線を画す児童文学タイムトラベルものの面白さがここにはあります。
両親が仕事で外国に行ってしまう夏休み。十二歳の少年ドルーは、サマーキャンプに行くか、ブライズ叔母さんの家に行くかの選択を迫られて後者を選びました。意地悪な子と夏休みも顔を合わせるよりは、賢明な選択でした。ミズーリ州にある叔母さんの古い家。ドルーの父親の叔母である六十歳を越えたブライズ叔母さんは、ここにドルーの曽祖父にあたるエドワードと二人で暮らしていました。しかし、不思議なことに、すっかり呆けているはずのエドワードは、ドルーを見るなり、やけに喧嘩腰の態度をとるのですが、理由はわかりません。一族の歴史が詰まった古い家。古い家族写真に自分とそっくりの少年アンドルーを見つけたドルー(これは略称で実際はアンドルーなので同じ名前なのです)は不思議な気持ちになります。まだ子どもの頃に病気で死んだというアンドルーは、生きていれば、曽祖父と同じぐらいの年齢のはずでした。そして、彼が遺したビー玉をドルーは手にすることになるのです。その晩、叔母さんの家で寝ようとしていたドルーは、屋根裏部屋から突然現れた少年に、ビー玉を盗んだと言いがかりをつけられます。それは、写真で見た少年アンドルーでした。乱暴で強気な少年はドルーを威嚇しますが、どうやらアンドルーもこの事態に困惑しています。そして、ドルーに自分がジフテリアにかかり瀕死の状態でベットに寝ていたことを打ち明けるのです。急いで叔母さんを呼びに行こうとしたドルーは昏倒し、気づいた時には、自分が1910年の世界でアンドルーと入れ替わっていました。ドルーはこの事態に慄きながら、アンドルーのフリをして、この時代の少年として生きることになります。悪ガキだっアンドルーが急に大人しく真面目な少年になってしまったことに家族は戸惑います。アンドルーの弟のテオは男らしくない兄に幻滅しますが、アンドルーの姉のハンナは、急に大人しくなった弟に優しく接してくれました。未来のことを口にしてはいけないと堅く自分に言い聞かせながら、アンドルーと再び入れ替われるように願うドルー。しかし、彼の前にはアンドルーのライバルである悪ガキ、従兄弟のエドワードが立ち塞がり、挑発してくるのです。さて、現代の大人しい少年、ドルーは、男の子が乱暴であることがデフォルトのこの時代でどう振る舞ったのでしょうか。
海外児童文学における「サマーキャンプ」とはなにか。夏休みに開催される子どもたちの合宿。そこは人間関係の坩堝であり、弱肉強食の世界でもあります。そこまでではなくても、コミュニケーション能力や社交性が問われる場所なのです。それは児童文学やYAの主人公になるようなタイプの子どもたちにとっての鬼門です。基本、彼らはサマーキャンプに馴染めないのです。サマーキャンプでひどい目に逢うか、サマーキャンプを抜け出す、ということが題材としては良く使われます。おそらくは過去の時代のアンドリューは、サマーキャンプを大いに楽しめるタイプであり、現代のアンドリューは、典型的な児童文学の主人公です。この物語も、サマーキャップを避けたことが、主人公の心の冒険のきっかけとなります。まったく違うタイプの二人の少年は対立します。しかし、時代を越えて、このタイムトラベルの当事者同士として、互いの立場を経験したことでの成長と仲間意識が生まれるというのが読みどころです。ということで、環境の違う場所に無理やり放り込まれる、という体験が人間を強くし、成長させるのであるならば、身近なところでは、それはサマーキャンプではないのか、という気もしてきます。タイムトラベルを克服するよりも、サマーキャンプを克服す方がまだ容易でしょう。ちなみに楽しいサマーキャンプの物語もあります。サマーキャンプを悪者にしがちですが、幸福なサードプレイスにもなりうるという可能性も捨てがたいのです。