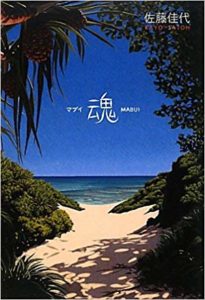 |
出 版 社: 金の星社 著 者: 佐藤佳代 発 行 年: 2009年11月 |
< 魂(マブイ) 紹介と感想>
沖縄県の失業率が全国平均に比べて高いのは「仕事がない」だけが理由ではなく、「働かなくても大丈夫」と思っている人が多いから、という勝手な説があります。県民性への偏見にみちた妄言かも知れませんが、何事にも捉われない沖縄のライフスタイルへの憧れから、そんなふうに思う人もいるのだろうか、などとも考えてしまいます。本土とは考え方の違う浮世離れした場所としての沖縄。離島はさらに楽園めいたところのように思えます。そこに流れるゆったりとした時間は人間を本来の姿に解放する。沖縄だって都市部には犯罪もあるだろうし、田舎に行けば閉鎖性もあるのでしょう。ただのノンキな場所ではないはず。それでも、大いなる自然の源であり、人間の根元や魂に近い場所なのではないかという幻想はあります。沖縄についての児童文学は、その歴史と戦争について語る時代を過ぎて、神秘や沖縄的な心の在り方の方にフォーカスされた物語の方がむしろ主流になってきているようです。池澤夏樹さんの作品や、ここ数年(2010年前後)では課題図書にもなった早見裕司さんの『となりのウチナンチュー』、また池上永一さんの作品などもYA的に読まれることも多いようです。沖縄的な価値観と、現代のYAが出会う時、不思議なハーモニーが生じますね。今年(2010年)刊行された末吉暁子さんの『赤い髪のミウ』も沖縄が舞台でした。心の世界の広がりを感じさせてくれるような児童文学作品に出会えるのではないかという期待感が沖縄モノにはあります。そして、昨年(2009年)発行された佐藤佳代さんによる本書もまた、そうした沖縄のスピリットを取り込んだ児童文学作品でした。
沖縄の石垣島から、さらに船でしか行けない離島に暮らす七海。仕事の関係で一緒に住むことができない両親と離れて、七海は祖父母と、母の年の離れた弟であるアキラニィニィに育てられました。島の自然の中でのびやかに育った七海でしたが、九歳の時、なんとか仕事の都合をつけた両親によって、東京で一緒に暮らすことを提案されます。島を離れたくなかった七海は、しかたなく東京に移り住むことになるのですが、言葉や文化の違いもあり、東京の学校になじめず、イジメられて島に帰りたいと願うのです。七海が寂しく悲しい思いをしている時、島から駆けつけてくれたのはアキラニィニィでした。中学を出て、すぐ漁師になったアキラニィニィは優しく、いつも七海のことを思いやっていてくれました。アキラニィニィの励ましもあって、心を強く持ち、次第に東京の暮らしにも慣れていく七海でしたが、やがてニィニィに悲しいことが起ったことを伝えられます・・・。
沖縄の子が都会に行くことで生じる軋轢や、都会の人間が沖縄の島の村社会に入っていくことの難しさもこの物語では描かれています。どうにも排他的で、ヨソモノが入っていくには難しい場所もあるというのが、人間世界の現実です。そうした辛さや難しさを越えていくには、しっかりと心の幹を持ち、生活の場所に根をはっていることが必要とされます。沖縄の言葉で言うところの魂(マブイ)とは、生きている人の魂であり、つまり、生きている「心」そのものかも知れない。そんな魂の実在を信じることが人間に力を与えます。魂がやってきて、帰っていく場所、異郷ニライカナ。そこで人間の魂は永続していく。出会いも別れも、すべてが繰り返されていく。本書は、物語としての完成度や面白さでは、やや物足りないところを感じるのですが、そうした魂の輪廻や、壮大なスピリットが全面にみなぎる作品であり、静かな祈りに満ちた作品です。人間が生きていくには色々な形で痛み恨を感じざるをえません。けれど、いつかまた心は安らかになり、穏やかな時を迎えられます。誰も楽園に暮らし続けることはできず、人はいつか「島を離れる」時がきます。そんなパラダイス・ロストを経験しても、目に見えない楽園を心に持っている人間は、どんな場所でも、どんな辛いことがあって、その魂を輝かせることができる。この物語の伝えるところを僕はそんなふうに感じ取っているのですが、読み手次第というか、かなり多義的に解釈できる物語ではないかなと思える作品です。