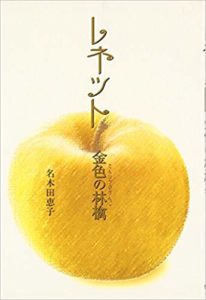 |
出 版 社: 金の星社 著 者: 名木田恵子 発 行 年: 2006年12月 |
< レネット 紹介と感想 >
ひとつの家族に埋めようのない大きな風穴を開けてしまった出来事。それは、まだ十二歳だった少年の事故死でした。母親は力を失い、父親は自分の犯した失敗と責任に苛まれる日々。そして、妹の海歌(みか)は、兄を亡くした失意を感じながらも、自分が両親にとって、兄以上の大切な存在ではないことを知る二重の痛みを感じていました。海歌の心は複雑にねじれています。兄の事故死を契機とした両親の不仲は次第に深まり、そんな渦中にありながらも、父は夏休みに「保養」を目的に日本を訪れるロシアの少年のためのホームステイ先として、自分の家に招くことを決めてしまいます。何故、少年には「保養」が必要なのか。それは海歌が生まれた翌日に発生した世界的な事件、チェルノブイリ原発事故が及ぼした影響です。事故を遠因に両親を失った少年は、祖父と一緒に、未だに放射能に汚染された地域に暮らしています。こうした地域に住む子どもたちに、自然に恵まれた北海道での「保養」を与え、体力を増進させることを目的に、日本人のボランティアグループは活動していました。海歌の父もまた、その活動に感化され、いや、もしかすると、亡くした息子と同い年の少年を招くことで、なにか心の中を埋め合わせようとしたのかも知れません。当初、反対していた母も、灰色の顔をしてやってきた少年、セリョージャに心を開き、その身体を気遣うようになります。ただ海歌だけが、両親の気持ちをはかりかね、複雑な思いを抱えて素直になれない自分を持て余したままセリョージャに接していきます。
通じない言葉で、伝わらない気持ちを手繰り寄せながら、海歌はセリョージャに次第に強く惹かれていく自分を感じます。重い宿命を背負いながら、人を思いやる心をもった優しい少年。母親から受け継いだ希望のりんごの種を胸にいだいて、海歌に暖かい言葉でよびかけるセリョージャ。でも、このホームステイの期間が終わってしまえば、彼は放射性物質が残留する祖父の待つ居住地に戻らなくてはならないのです。それは「保養」で養われた健康が、再び、失われることを意味しています。帰国後のセリョージャの安否を知ることを恐れたまま、海歌は長い月日を重ねていきます。海歌が心の中に鎮めた錨は、重く、ずっと彼女の胸をふさいでいます。未解決な気持ちを抱えたまま二十歳になった海歌が、再び、過去の扉を叩こうとするところから、この物語は始まります。知ろうと思わなければ、悲しい「事実」に打ちのめされることもない。でも、いつかあったはずの大切な気持ちも封印したまま生きることも、人を灰色の世界に置きざりにする。勇気をふりしぼりながら、扉をあけようとする海歌の姿を一緒に見守る。そんな胸にせまる物語です。
広島型原子爆弾の数百倍の放射能を周囲に放出する大惨事となったチェルノブイリ原子力発電所の火災事故が起きたのは、1986年。この本の発行から二十年前になります。まだソビエト連邦が存在していた時代のウクライナ共和国での事故。被害にあったのは当該施設に勤務していた人々や、救助等にあたった二十万人のみならず、近隣の住人数百万人にも及ぶと言われています。放射線障害の影響による死者は数万人と推定されているものの、正確なことはわからず、汚染された地域に住み続けることで、残留放射能による二次被害を継続的に受け続ける人たちが、将来、死に至る病を発症する可能性を思えば、その数字はどこまで拡張されるのか想像もできません。歴史的な大惨事もまた、そこに関わった人間、ひとりひとりの心の事件でもあるというのは、同じく大きな原発事故を体験することになった日本人には、直接の当自者ではなくても慮れることではないかと思います。目を覆いたくなるような悲しいことが世の中にはあって、ありすぎて、どこまで目をそらさずにいられるものなのかと思ってしまいます。鋭敏すぎる感受性をもって世界を見つめるとき、あまりにも悲痛な運命への共感は心の許容量を越えてしまうものかも知れません。鈍感であることの効用を思いはするものの、あえて見つめようと思わなければいいのか。傍観しながら、受け流していられるのか。悲痛な運命と戦っている人に思いを寄せる時、自分もまた、ともに戦っているのです。どこか遠くの国に暮らす大切な人を想う時、世界は思いのほか小さく感じられる。それはまた、世界中が日本に寄せてくれている思いかも知れません。