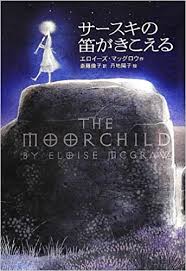 |
出 版 社: 偕成社 著 者: エロイーズ・マッグロウ 翻 訳 者: 斎藤倫子 発 行 年: 2012年06月 |
< サースキの笛がきこえる 紹介と感想>
「お前は橋の下で拾ってきた子どもだ」なんて、親にからかわれたのは、昭和時代に育った年代の方ぐらいまでかと思います。それほど捨て子が一般的だったのかどうかは今となっては謎ですが、コインロッカーベイビーや赤ちゃんポストなどを経由すると、そんな冗談も言いにくくなった時代の変遷を感じます。一方で、欧米の小説に良く登場するのが、チェンジリングです。「お前は妖精の取り替えっ子だ」なんて言われるのは、親に似ない、どこか変わったところのある鬼っこである所以です。またここでいう妖精は、翅のある美しい者というよりは、良いものでも悪いものでもない、野良の小鬼です。この物語の主人公であるサースキは、妖精の取り替えっ子じゃないのか、と噂されるような、ちょっと変な子です。そして、実際、赤ん坊の時にすり替えられた子どもだったのです。しかも、人間の赤ん坊の方ではなく、代わりに入れ替えられた妖精なのです。しかし、本人には妖精であった頃の記憶はなく、自分を人間だと疑っていません。変わり者で、周囲につまはじきにされている少女。特別な力などないのに、異質であるために人からは避けられてしまう。そんな嫌われものの女の子が、村の人気者の少年に愛されて美しく変わっていく、というストーリーで思い出すのはジョルジュ・サンドの古典名作『愛の妖精』です。それは、この物語とはまったく違う世界線のロマンスです。ここでは現代的エッセンスで、妖精の取り替えっ子の物語が語られていきます。自分の居場所がなく、周囲とは違和感があって生きづらい。そんな少女が、強い意志を持って、毅然と自分の為すべきことを為します。どこか寂しく、切ないストーリーです。今はいない、サースキのことを誰か覚えていてくれるだろうか。胸に灯ったものをずっと温めていたいような素敵な物語です。
鍛冶屋の娘、サースキは奇妙な姿をした風変わりな女の子でした。村の他の子たちとは違って、浅黒く、やせていて小柄で、手の指も足の指も異様に長い。そして彼女の目は、その気分を表して、灰色から緑色まで色が変わるのです。人からはじろじろと見られて、十字を切られることもあるサースキ。村に何か悪いことがあれば、すぐにサースキのせいだとされてしまう不吉な子。じっとおとなしくしていることがなく、すぐに荒れ地に遊びに行ってしまうサースキには両親も手を焼いています。近所の大人も子どもたちも、サースキのことを、妖精の取り替えっ子ではないのかといぶかしく思っていました。気味の悪い変な子。他の子たちからは仲間はずれにされたサースキは、淋しさにたえながら、それでもたくましく育っていきました。サースキにはあり余る力があり、それを発散するために荒れ地を歩き回りますが、そんな姿は余計、村の人たちから不審を向けられるため、両親からも止められてしまいます。無聊を持て余したサースキは、屋根裏で祖父のバクパイプを吹くようになります。誰からも教えられたことがないのに風笛曲を奏でられるサースキ。それもまた悪魔の音楽みたいな曲だと言われてしまうのです。村の子どもたちに伝染病が流行り、サースキのかけた呪いだと噂されます。村人たちは、夏至祭の前夜に「丘の火」にサースキを投げ込むといきりたちます。もはやこの村から出ていかなければならないほど追い詰められてしまったサースキ。居場所を失った少女が決意したのは、それでも自分を愛してくれた両親のために、自分のやれることをやることでした。
サースキは自分の正体に少しずつ気づいていました。水鏡に映った自分の奇妙な姿。断片的にではあれ、どうして自分にはルーン文字が読めるのか。放浪の民の占い師が、サースキの掌を見ても、手相を見ることができないと言ったのは何故か。どうして荒れ地に惹かれるのか。なによりも、普通の人間の目では捉えられない妖精を、サースキは見ることができるのです。妖精はサースキが吹いているのは妖精の国の曲だと言います。やがてサースキは自分がつて妖精であった記憶をとりもどしていきます。妖精の母親と人間の父親を持つ半人半妖であるサースキは、妖精としての充分な能力がなく、妖精の国を追放されて、人間の赤ん坊と入れ替えられてしまったのです。妖精と人間、どちらの世界にも居場所がないサースキ。それでも、赤ん坊の頃から、サースキを取り替えっ子ではないかと疑いながらも、ずっと親身でいてくれた祖母や、サースキに手を焼きながらも愛情を注いでくれた両親がいました。村を出て行く前に、サースキは、自分と入れ替えられてしまった両親の本当の子どもを取り戻すために、自分を追放した妖精の国へと赴きます。人間でも、妖精でもなく、どこにも居場所もない自分への諦め。そこから、サースキがふるわせる勇気と、闘う覚悟が胸を打ちます。物語の救いは、サースキが十一歳の春、身寄りのない少年タムが鋳かけ屋のプルーマンに連れられて、村にやってきたことです。羊の世話をするタムと出会ったサースキは、他の子どもたちのように彼女を避けない彼と親しく言葉を交わすようになります。タムと笛と一緒にバグパイプを合奏するサースキの姿など、なんとも愛おしく思えます。やがて、冒険の果てに村を去っていくサースキのそばにタムがいることを、なんとも嬉しく感じます。サースキの幸福を祈らずにはいられない、そんな愛おしさを感じられる物語です。