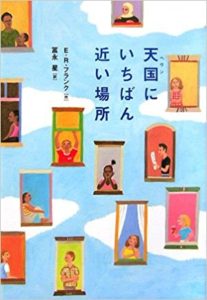 |
出 版 社: ポプラ社 著 者: E.R.フランク 翻 訳 者: 冨永星 発 行 年: 2006年09月 |
< 天国にいちばん近い場所 紹介と感想 >
「わたしって、最低」と、うそぶく、自称「最低人間」の皆さん、こんにちは。いや、ちょっと酷い言い方でしたね、ごめんなさい。自分を「最低」と言いたくなる時期も人生にはあるかと思います。自分の劣悪な人間性を認め、というよりは、貶めて口にする言葉としては、胸に痛いフレーズです。自分で言っておきながら、自分で傷つくことすらあります。それでもあえて口にするのは、誰かに「そんなことないよ」と言って欲しいのか、それとも、これ以上、人から傷つけられないための先取防衛なのか、「最低な自分」を表明することの意味を思います。真の「最低」とは何か。ドラックに溺れ、学校にもいかず、自堕落な生活を送りながら、自分の「最低ぶり」を見つめている子もいれば、敬虔な信仰を持ち、禁欲的に暮らしていながら、それでも自分の中の抑えきれない心の動きに「最低」を感じとってしまう子もいます。どうしても、いい子にはなれない。誰からも愛されるような、優しく、広い心を持った人間にはなれない。理不尽な出来事。暴力を振るう親。薬やアルコールに溺れる親。仲たがいする両親。偏見に満ちた態度を、自分の友だちにとる親。でも、自分は子どもで、力のない子どもで、どうにもすることができない。正しい軌道からはずれてしまった世界を、もとに戻すことはできない。抑え切れない気持ちに翻弄される。すべては自分のせいかも知れない。だから、悪いことだとわかっていてもやってしまう。時として、最低な自分とつきあいながら、それでも、なんとか周囲の世界とわたりあおうとする。そんなティーンエイジャーたちの溢れだすような気持ちが、ここに、つなぎとめられています。参ったなあ、どうしたらいいんだろう。本書『天国にいちばん近い場所』は、大人もまた古傷が疼くような、かつての、生真面目で気恥ずかしい、ちょっと戸惑ってしまうような、そんな感情のおののきに満ちた作品なのです。グッジョブ。
十一人の子どもたちによる七年間の物語。小学校高学年から高校卒業ぐらいまで、の時間が描かれていきます。人種も家庭環境も違う少年少女、それぞれの視点から語られる物語は、時として絡み合い、前の物語で脇役であった子が、主役のバトンを受け取り、自分の物語を語りついでいきます。それぞれの物想いは、時間の経過とともに解決されたり、様々な隘路に陥ったり、主人公を異にする連作短編でありながら、相互に作用して、アメリカの現代を生きる子どもたちの心の世界を活写します。手放しで、危なっかしく、奔放で、それでいて弱くいとけない心の動きは、見ていられないような、不安感や緊張感を伴います。とはいえ、多くの共感をもって本国のティーンに歓迎されたという、本書が描く「気分」は、ぐっと心に迫ってくるものがあるのです。均等に描かれる多数の少年少女の、誰かしらに心を寄せられるのかも知れません。白人の美少女、であること。モスリム、であること。母を殴り続ける父親、の息子であること。妊娠している、十六歳であるということ。殺人鬼みたいな目をした、少年であるということ。情動が不安定で、ただただ笑い続けるしかない少年であるということ。それぞれが手一杯の荷持を抱えながら、目の端で、他の誰かが必死に生き抜いている姿に、視線を落としている。誰かが誰かを見つめている。互いの事情を完全に理解できるわけではない。時には、自分を呪い、罵り、他人を嫉妬し、羨み、未解決な自分の問題だけで精一杯な時間を、生きている。それでも、誰かの側にいて、微かに心が触れ合う瞬間はある。言葉にはされないけれど、淡い、その瞬間の喜びで満たされることもある。はりつめた心が一呼吸できるような瞬間。はっきりと言葉で結ぶことができない、ふと、気持ちがほどけていく一瞬が、妙に心地よく感じられるのです。自分をなじりながら、生きなければ、世界とのバランスがとれない時間もある。それはとても哀しいことなのだけれど、きたるべき世界がきっとある、それは少なからず明るいものであって欲しいと願いたくなります。
この作品の大人たちもまた、決して、幸せではない時間を生きています。エリックとミッキー兄弟の母親は、子どもたちから引き離され、麻薬中毒からの治療プログラムを受けなければなりませんでした。そんな母親に代わって、弟の面倒を見続けるエリックも、マリファナの常習者で、世間の「偏見」や「哀れみ」から身を守るために、絶えず、闘う姿勢を崩しません。エリックもまた、無軌道で不幸な大人の一人となってしまう予感を感じさせながらも、無邪気な八歳年下の弟のために、精一杯、自分を立て直そうとしています。ギリギリのエッジを生きる少年の物語。そんなエリックを見つめる、かつて兄を病気で失った少女の視線。かたくなで、心を通わせることが難しいエリックに、歩み寄ろうとする少女の物語がクロスしていきます。そこには、また息子を失ったことのある少女の両親が、この「哀れむべき」兄弟を、入院した母親に代わり、預り育てる心のドラマも存在します。輻輳する心の波動が、結びつき、離れ、やがて、微かに心を軽くする時間を迎えられるのか。できすぎた話はひとつもなく、奇跡も起きない、あたり前の世界を生き抜いていく子どもたちの心のゆらぎをつなぎとめた、薄い氷のような繊細な作品です。ふう。