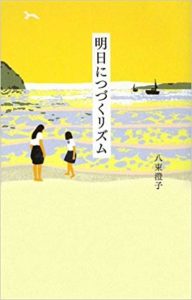 |
出 版 社: ポプラ社 著 者: 八束澄子 発 行 年: 2009年08月 |
< 明日につづくリズム 紹介と感想 >
広島県因島市。それは2006年に尾道市に編入されたことで消滅した自治体の名称です。因島という島がひとつの市を形成していることに誇りを持っていた島民にとっては、因島市の名称が無くなることは痛恨の出来事でした。その市町村統合を来春に控えた因島で、進路に悩んでいる中学三年生がいます。因島に住む中学生は、高校進学に際して固有の選択肢があります。このまま島にある唯一の公立高校に進むか、島を出て本土の高校に通うか。家の経済状態を考えると、おのずと方向性は決まってきますが、ここで「島を出たい」という希望が、子どもたちの胸には灯ります。島暮らしの閉塞感から抜け出したい。何か不満があるわけではないけれど、広い世界に出ていってみたいと思うのが若さかも知れません。島を出てどうするのか。自分は一体、何になりたいのだろう。自分には何ができるのか。短距離とはいえ「海を越える」進路の選択には相応の覚悟が必要です。島に暮らす、中学三年生の千波もまた、この岐路に立っていました。これからどうしたいのか。漠然とした希望はあるけれど、決めることは難しいのです。美しい自然の風景に囲まれ、牧歌的な地域コミュニティで暮らす千波の生活は、自分のような都会育ちからすると羨ましく思えるのですが、そこには「島」という閉鎖環境に縛られている閉塞感もあるのかも知れません。そんな彼女の心を慰めてくれているのは、親友の恵と、二人が大好きなミュージシャン「ポルノグラフティ」です。ご当地、因島の出身であるポルノグラフティの歌に二人は励まされ、いつかファンレターを書こうと思いながら果たせないでいました。活き活きとした方言で交わされる会話や、眼に浮かんでくるような美しい島の情景、ごく平凡な中学生である千波の心情など、あたりまえでいて、大切な、愛おしいものがここにつなぎ留められた物語です。
千波は進路のことだけでなく、弟の大地の存在にも心を乱されています。大地は両親が施設から譲り受けた男の子です。聞き分けがなく、やんちゃな大地に手を焼いている千波には、両親が縁もゆかりもない大地を里子にした理由がわかりません。大地を憎らしく思いながらも、大地を可愛がってあげられない自分にも腹が立ってしまう千波。母親の、のぶ子のように優しく大らかになれない自分を持て余しているのです。それでも、本当の両親の愛情を知らず育った大地の悲しみや、たよりなく生きている存在感に、いとおしさを覚えていく千波。一足飛びにはいかないけれど、少しずつ大地との距離を縮めていく千波の心の動きがつぶさに描かれていきます。そのあたり、実に読まされます。大地が『くまさん』(まどみちお作)の詩を朗読するのを聞いて、母ののぶ子と千波が感動する場面があって、ここは読者である自分もぐっときました。「そうだ ぼくは くまだった よかったな」と結ばれる自己肯定の詩です。これは、まどみちおスピリットの真髄で、たとえば『ぞうさん』もそう解釈されますが、お鼻が長いのは母さんと一緒で、そんな自分を誇らしく思っている子どもの気持ちがあらわれています。『うさぎ』の「うさぎに うまれて うれしい うさぎ」にも共通するものです。無邪気に詩を朗読する大地に、その生い立ちを重ねると、のぶ子や千波ならずとも、思いいたるところがあるはずです。千波もまた、どこか自分を肯定できないでいます。そんな娘を見つめる、のぶ子の視線もまた優しく、惑える子どもたちが、親の愛情にしっかり守られていることに深く安堵させられます。千波がいろいろな気持ちに揺れながらも成長していく物語なのですが、心は広くおおらかになったり、狭く意固地になることもあります。平凡な中学生はごく等身大で悩み、喜んだり、拗ねたり、素直になったり、悲しかったり、嬉しかったりする。そうしたすべての自分を肯定していくことに戸惑いながら、それでも前に歩んでいく千波の一歩一歩が、豊かな筆力で描き出されていく見事な作品です。
ここではないどこか、に希望を求める時代は終わって、どこかではないここ、を愛する地元志向が強くなっていると言われている昨今(2018年)です。SNSでずっと地元の友だちとつながっていられるから、新しい友だちはいらないなんて、まことしやかに現代の若者像が語られたりしますが、たしかに内向きに閉じはじめているのが、このところの潮流かも知れません。「書を捨てよ、町に出よう」や「家出のすすめ」的な、かつてのメッセージは、若者にとって、今もまた有効なのだろうかと考えます。とはいえ、故郷に唾棄することも、訣別する必要もなく、地元を愛することは否定すべきことではありません。チャレンジスピリットは推奨されるべきですが、何かを捨てる必要もないのだろうと思います。
自分は都会生まれの都会育ちですが、出身地には愛憎半ばするところがあります。それはどこか子ども時代の自分を肯定できないでいる気持ちのあらわれかと思います。この物語には、子どもである自分を、自ら愛していくということを考えさせられます。千波もまた自己肯定できないでいる子ではあるのですが、弟の大地の寄る辺ない心を感じとって、大地をいとおしく思います。大地だけではなく、両親や友だちやこの島の人たち、自分をとりまくすべての環境に思いをはせる時、千波の心の変化が目に映るものを変えていきます。自分がゼロではいくら掛け算しても答えはゼロです。自分をいとおしく思い、大切にすることで、世界の広がりは無限になるのかも知れません。そして、自分の人生を最良なものにするために進路を選択しなければならない。その大事な局面で、弟の大地を通じて、自分自身を肯定することを言外に感じとっていく千波。市町村統合という、島のひとつの時代が迫る緊迫感もまた相乗効果があります。そして傍らにはいつも「ポルノグラフティ」の音楽があって、背中を押してくれる。思春期の頃の、好きな音楽に心を寄せる気持ちもいとおしいものですね。実在の現役ミュージシャンを登場させていることで、特異な作品と思われてしまう懸念がありますが、この物語の中ではそれぞれが大切な要素で、こうした素材がすべて見事に連環していきます。実に味わい深い作品です。ちなみにこの作品も全国青少年感想文コンクールの中学生の部の課題図書に選ばれています。多くの中学生がこの本を読んだのだと思います。よかったな。