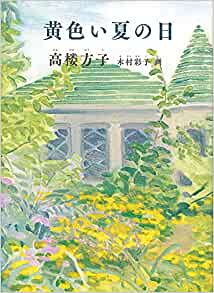 |
出 版 社: 福音館書店 著 者: 高楼方子 発 行 年: 2021年09月 |
< 黄色い夏の日 紹介と感想>
「耳なし芳一」はホラーの傑作です。その優れた音曲の才能を亡霊に魅入られてしまった琵琶法師の若者、芳一と、それに気づいて彼を救おうとする和尚さんの奮闘。亡霊に芳一が見えなくなるように、身体中に経文を書いたものの、耳だけ書き忘れるという、和尚さんのうっかりミスが悲劇を招く展開も秀逸ですが、耳を奪われたことで、芳一は運命との和解を見出したのではないか、という解釈の余白が残されているあたりも深みがあります。才能を認められたことは芳一にとっても歓喜すべきことであり、亡霊を求めたのは芳一自身ではなかったのかとか、そんな芳一への和尚さんの複雑な愛憎や嫉妬もあったのではないかとか、登場人物たちの思惑を勝手に想像してロマンはより深まります(もはや二次創作の世界ですが)。魔に魅入られるということの恍惚。禍々しいものに惹かれてしまうことの陶酔。更には、自分を理解し、受けとめて欲しいという、人間の心の渇望も見出せます。この『黄色い夏の日』の感想を書くのに「耳なし芳一」から始めるのはどうかしているのですが、ここではないどこかの世界の人たちに強く心を惹かれていく主人公と、憑かれてしまった彼の様子を見守りながら、いてもたってもいられない幼なじみとの関係性に、オーバーラップさせてみました。どうしても心を惹き寄せられてしまう、焦がれるような憧憬の念。これ以上、近づくのは危険だとわかりながら、吸い寄せられてしまう人間の性。不思議な古い屋敷、もうひとつの庭、憧れてしまう側の強い気持ち。高楼方子さんの名作『時計坂の家』とも二重映しになるノスタルジックなファンタジーです。そこに郷愁があるのは、不思議な回廊が通じた先が昭和前葉という懐かしい近過去だっただけではなく、いつか思春期に覚えた胸の痛みや高鳴りが息づいている場所でもあるからでしょう。閉じられていた日記の鍵が開いた時、消されたはずの過去の想いが、夏の陽射しのように眩く溢れ出します。これを受け止める読書時間のなんと甘美で濃厚なこと。実に圧巻の一冊です。
初夏の北の街。中学一年生の景介がスケッチブックを抱えて向かった先は、以前に見かけて心を惹かれていた一軒の家でした。三角帽子を思わせる尖り屋根。どこか童話的な意匠を凝らされた古色を帯びた趣きのある家。美術部の課題スケッチでこの家を描こうと思っていた景介は、その家の珍しい名字の表札を見て、小さく驚きます。その家の主人は、祖母が入院していた病院の同室で親しくしていた老婦人であり、見舞いにきていた景介のことも覚えていてくれたのです。誘われるまま、家に招き入れられた景介は、老婦人に、鍵のついた古い日記帳を開けて欲しいと頼まれます。景介が苦闘のすえ、ついにその鍵が開いた時、家の奥から声が聞こえます。居眠りしてしまった老婦人を置いたまま、景介は声の主を探し、廊下の突き当たりのドアの向こうに立ち入ると、そこには華やかな女の子めいた部屋があり、ゆりあと名乗る美しい顔立ちの少女がいました。溌溂として輝く、奔放なゆりあに惹かれた景介は、目を覚ました老婦人に確かめることも気恥ずかしく、おそらく孫なのだろうと思ったまま、家を後にします。さて、この少女に我知らず心を奪われてしまった景介は、祖母の用を足すために再びこの家を訪れ、元編集者だった老婦人の大量の本を整理する仕事を手伝うことを請け負います。ゆりあに会えることを心待ちにするようになった景介ですが、かならずしも顔を合わせることはできません。やがて景介は、この家の庭の垣根の向こうにある隣家に住む、やや子という少女とも親しくなります。華やかなゆりあと生真面目なやや子。二人の少女とそれぞれ親しくしながらも、景介は次第に、ある疑念を抱き始めます。彼女たちとの会話や持ち物から、ここが現実の世界ではないことに景介は静かに気づき始めていたのです。ただそれをはっきりとさせることを景介はためらいます。現実と幻想のあわいで翻弄される少年の日々が、美しい夏の情景をバックに描き出されていきます。
それぞれの登場人物たちのまなざしが交錯していきます。やや子は隣家に住む、華やかなお嬢様であるゆりあに憧れながらどこか反感を抱いているのは、景介がゆりあに惹かれていることを感じとっているからでしょう。景介は、自分の意見をしっかりと持った、やや子に尊敬の気持ちを抱いていますが、真っ当でリベラルな考え方を貫く彼女は「時代にそぐわない」少女であり、周囲の理解を得られないことに不満を抱いています。孤独な彼女が理解者を求める気持ちの切実さや、自分にはないものを持った、ゆりあのような少女への憧憬には、痛みを覚えます。その想いの強さは、時間を越えて、景介を惑わせていきます。二人の少女の間で戸惑う景介の挙動もまた、同じ美術部の、幼なじみでもある晶子に不審に思われます。景介のことが気になる晶子は、密かに彼が足しげく通う、昭和初期に著名な建築家に作られたという趣きのある、あの家を訪ね、その来歴を知ることになります。複雑に絡み合った過去の事情が明らかになりながらも判然とせず、道理に合わない不思議な縁起によって、物語は危うく成り立っています。きんぽうげ(バタカップ)の黄色い花に囲まれたその家に潜むのは、若き建築家の情念でもあったのか。氾濫するイメージと幻想的なメタファーに彩られた、思春期の何かにどうしようもなく憧れ、焦がされる気持ちを繋ぎとめた物語です。清新さを感じさせながらも、老婦人の人生を俯瞰するまなざしは『時計坂の家』より深まったものであり、四半世紀以上を経た作者の円熟もここに結ばれています。