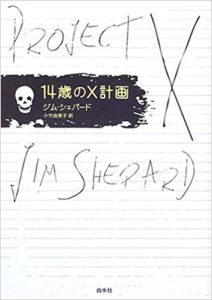 |
出 版 社: 白水社 著 者: ジム・シェパード 翻 訳 者: 小竹由美子 発 行 年: 2005年04月 |
< 14歳のX計画 紹介と感想 >
エドウィンは学校で孤立していました。それなのに「やってらんない」場所である学校に通わなければならない。いえ、誰からも認められていないわけではないのです。唯一の友人であるフレイクもいるし、エドウィンの絵の才能を認めて近づいてくる少女もいます。でも、エドウィンは学校の仲間たちと「うまくやる」ことはできません。教師には反抗を繰り返し、敵対する生徒たちと罵りあいを続けています。そして、友人のフレイクとともに、密かにこの「やってらんない」場所に対して、自分たちの「報復計画」をうちたて、それに向かって邁進していきます。『人生の鍵はバランスだ』と学校に貼られたポスターが暗示するものは何か。バランスをとろうなどとは思わない。二人の少年の心の迷走は、もはや止まらなくなっていたのです。「銃による無差別殺人」。一足跳びすぎる結論です。いや、今まで自分を見下していた連中を見返すには充分な報復なのか。彼らがそこにいたった動機を、子どもの「甘え」と指摘することも、「周囲の無理解」と指摘することもできますが、事件に至る過程をじっくりとトレースして見れば、また違った見方もできるかも知れません。必然性がまったくなかった(と思われる)犯行を決行することに、「彼ら」は、どの時点から「引き返す」ことが出来なくなってしまったのでしょうか。
本書は、アメリカのコロンバイン高校でおきた生徒による無差別銃殺を思い起こさせるような、二人の少年による「世の中への復讐計画」が、犯人である少年エドウィンの独白によって語られていきます。コロンバイン高校の「トレンチコートマフィア」と呼ばれた少年たちが、体育会系の生徒からのイジメを受け、学校中からつまはじきにされた仕返しに、無差別に生徒、教師を銃撃し、多くの死傷者を出した事件は衝撃的で、まだ記憶にも残っています。この物語も、学校という場所に自分たちを見出せない少年二人が、もやもやとした日常の中で、次第に「復讐計画」を積み上げていく過程が、リアルな会話の中で描かれていきます。しかも、ハイスクールの学生ではない、さらに年少の14歳という幼さ。「銃社会」というものが抱える問題も考えさせられますが、銃を撃つのは、あくまでも「人」であるということは事実でしょう。そして、この作品の恐ろしさは、煮つまりながらも、意外に冷静な子どもたちの心理にあるのかも知れません。
イジメへの加担の程度と、罪の意識は比例するものではないし、報復による被害にあった全員の、身体の傷と心の傷の軽重も、比例するものでもないでしょう。心の問題は、それまでの加害者との「関係性」によるものですが、積極的にイジメていた生徒も、イジメを見て見ぬふりをしていた生徒も、ここに関わってしまったかぎり、なんらかの心の負荷を負ってしまう。積極的な加害者ではなくとも、教室という場を共有していた「関係者」の一人にされてしまうという逃れられない宿命。学校、のみならず「集団の場の力学」は自然と習得されて、個人として「生き抜く」ための知恵を授けてくれるもの。要は『人生の鍵はバランス』か。関わらない、という処世術も、生き抜くために必要かも知れません。出来れば、正義漢でありたいと思いますが、強くイジメを否定する勇気は、僕にはあるか。「関わりを持ちたくない」関係者の一人、として、それでも関係してしまうことも往々にあるかと思います。人間関係のドグマ。自分もまた加害者となりうる可能性はある。自分の暗黒面も、また、冷静に見つめないと「人を許せる人間」になれないそうですが、自分がそこまで達観しているか、どうか、まだ半信半疑というところです。自分自身が抱える心の闇ゆえに、こうした物語に惹かれるところは、あるのかも知れません。