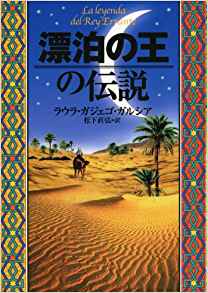 |
出 版 社: 偕成社 著 者: ラウラ・ガジェゴ・ガルシア 翻 訳 者: 松下直弘 発 行 年: 2008年03月 |
< 漂泊の王の伝説 紹介と感想 >
今は昔。そんな説話物語の舞台となるような歴史の時代に一人の王子がいて、彼が「漂泊の王(マリク)」となるまでの軌跡が語られるのが前半、130ページ。さまよえる魂が、ついに留まるところを知り、運命の辻褄がすべて合うまでが後半、170ページ。ということで、読みごたえのある300ページの物語は、一人の王子の驕慢が為した罪と、激しい悔恨を描き出し、読者を心震させます。そして、読者もまた、物語を読むことで、王子の同伴者として、贖罪の長い心の旅の果てに「浄化」の時を迎えるのです。恩讐の彼方にあったものは、少なからず幸福な結末でしたが、ただそこに至るまでの過程で経なければならない「受苦」は相当なもので、己自身の罪業を「認知」させられる主人公の苦闘は激しく、狂おしい悲劇的緊張感に満ちあふれていました。などと、ペダンティックな書き方をしながら匂わせているのは、この砂漠をさまよう王子と幻惑的な力を持つ絨毯の物語が、所謂、歴史ファンタジーではなく、古典的な運命劇であるということです。しかし、星々の導きや神々の託宣によって、命運が尽きてしまうような古典的な王侯の悲劇ではない。激しい葛藤と内省をもって人間が成長し、たとえ愚かな罪を犯したことがあったとしても、それでも人は赦されうるのだという「救い」がここにはあったかと思います。運命との「優しい和解」もまた、古代ならぬ現代に描かれた詩劇としては、しかるべきものなのかも知れません。つきつめれば、運命もまた絶対ではない。我々人間はさだめの鎖の虜なのではなく、未知の可能性のうちに未来があり、その岐路としての現在があるのだという、望むべき運命を己自身で手繰り寄せる希望のメッセージにあふれた物語でもありました。実に読み応えのある作品。ネット上でも多くの「面白い」との声があがっているのを見かけます。どんなお話なのだろうかと期待していましたが、思いのほかクラシックで、そして、力強い、満足のいく作品でした。ぐいぐいと引きつけられる心の彷徨の物語でしたよ。ほう。
時は古代。キンダ王国の王子ワリードは、武に長け、秀でた知性と探究心を持ち、なかんずく詩作を得意とする、才能にあふれた若者として、国王と臣下の信望を集めていました。ある時、己の詩作の実力を試すために、自ら主宰し参加した詩のコンクールで、王子は予想外の敗北を喫します。恋愛詩、叙景詩、称賛詩、いずれの項目でも、優勝者に及ばないとされた王子。果たして、優勝者は、貧しい絨毯織りの職人だったのです。名誉を奪われた失意の王子は、翌年、翌々年と、再びコンクールを催し、優勝者の絨毯織りの男、ハンマードに挑むものの、審査員たちは、王子ならぬ絨毯織りに軍配をあげます。自分の詩に足りないものはなにか、悩める王子は、審査員に招いた詩聖に教えを乞います。しかし、返ってきたのは、王子の詩には「心」がこめられていないという、王子にとっては意外な宣告でした。自分の詩のどこが、心がこもっていないというのか。何故、ハンマードは、自分の父である国王を称える詩に、息子である自分よりも心をこめられるのか。王子は、秘密を探るべく、伝承や国史を編纂する公職をハンマードに与え、実質、王宮に軟禁状態にします。ハンマードの秘密はわからないまま、王子の心に芽生えた嫉妬の焔は、ジリジリと自らの常軌を焼失させ、ハンマードを拘束し、自由を奪い、飼い殺しにしてしまうのです。故郷に帰りたいハンマードは、王子の無理難題に応えるため、己の命を削って仕事をし、そして、王子の赦しを得るために一枚の絨毯を編み上げます。哀れ、ハンマードは、妻と三人の息子の待つ故郷に戻ることができないまま、絨毯織りとしての鬼気を託して、この世のすべてである森羅万象を編みこんだ絨毯を遺して息絶えるのです。父王が亡くなり、王国を継承しながらも、政務に専心できないほど心を病んでしまっていた王子は、臣下の信望も失い、疑心に苛まれていました。本来は素直な気性を持っていたはずの王子は、絨毯織りの死に対して、一人の人間の人生を、自らの嫉妬により踏み潰してしまった責任を痛感します。やがて部下の裏切りにあい、ハンマードが遺した絨毯を奪われ、自らの王国をも見失った王子は、たった一人、砂漠を漂泊する旅を生きることになります。さて、あらかじめ心を失っていた王子は、果たして、この荒涼たる広い砂漠に、何を見つけ出すのでしょうか。
うっかり第一部をまとめてしまいました。このどんどんとエスカレートしていく王子の壊れっぷりの潔さよ。王宮での彼は、まさに我を失い、誰の諌言も進言も受け入れられない煮詰まった精神状態に入り込んでいました。一体、王子の犯した罪は「心神喪失状態だったので」ということで赦される類のものだったのでしょうか。「漂泊の王」となった王子は、素直に自らの罪を認めます。流れ流れて、盗賊、遊牧民、商人に身をやつしながら、王宮では知ることのなかった世界と出会い、感じ取ることのできなかったものと対面していきます。深い苦悩。そして、贖罪のために己の身を捧げても構わないという覚悟を持ちながら、我知らず第二の人生を生きていたのです。運命は偶然を装い、必然の出会いを「漂泊の王」に与えていきます。やがて、絨毯をとりもどすためのさすらいの日々は終わりを告げ、「漂泊の王」は自らを裁くために死地へと赴きます。そこで彼は何を見たのか・・・。ちょっと語りすぎましたが、思わず饒舌になってしまうほど、物語に酔うことのできる作品です。人を傷つけ、苛んでしまったという事実は消えない。自らをどんなに悔いても過去の時間は戻らない。しかし、人間には、まだ未来が残されている。そこにはあらゆる可能性があって、望むべき未来に向けて希望をつないでいくことはできる。そんなメッセージを強く感じとれる、背筋の伸びた清涼感に満ちた作品です。いや、砂漠に照り返す灼熱の太陽に焦がされ、喉の渇きを覚えるような、そんな熱さこそが身上であったか。意外なことに、この砂漠とラクダと絨毯と、古代の詩人の警句に溢れたアラビア半島の物語を書いたのは、スペイン人の作家なのです。日本人の新藤悦子さんが、中近東の歴史物を描かれるのもスペイン人にとっては意外かも知れませんが、スペインとアラビアの取り合わせには、ちょっと驚いておりました。