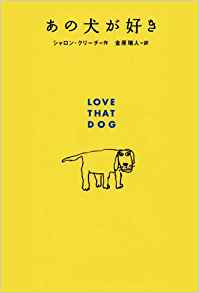 |
出 版 社: 偕成社 著 者: シャロン・クリーチ 翻 訳 者: 金原瑞人 発 行 年: 2008年10月 |
< あの犬が好き 紹介と感想 >
僕が小学四年生の時に国語の授業で、詩を書くという課題がありました。小学生の詩というのは、小賢しくなっては味がないものですが、かといってナチュラルなパッションを全開にするのも気恥ずかしくなってしまう年頃があるものです。その時、僕はペットのウサギがいかに可愛いか、ということを詩にしてみましたが、どうにも紋切り型で情けなくなるような出来で、いやそもそも詩心というのがなかったのですね。やがて、このウサギとは別れる時がくるのですが、その切なさは偲びがたく、色々な後悔もあって、ふいに前に書いた拙い詩が思い出されて泣けてくる、という始末。実際、そんな強い感情こそ言葉にのせて詩にできたらいいのだけれど、なかなかできることじゃないんですね。子どもの頃に母親が亡くなったことさえ、自分の中で未だに言葉で整理がついていないようなところもあるので、感情を表出するということの難しさを思います。まあ、拙い詩でも、そんな背景を読みとってもらえれば、ちょっとはグッとくるものがあるのやも知れず、ここに全文公開できれば良いのですが、さすがに記憶に残っていないのです。いや、そんな大したものではないな。
ということで、この作品を読んで、まさに、そうした記憶がまざまざと甦ってきたのです。小学生の男の子が、詩を書いている。イヤイヤ書いている。詩なんて、女の子の書くものだからって、恥ずかしいと言っている。その拙い、詩のような、日記のような文章が続くのですが、だんだんと、彼が、先生の読んでくれる有名な詩に影響されて、自分の想いを、言葉に乗せ始めるようになります。まずは換骨奪胎で、有名な詩の言葉を入れ替えているだけなんだけれど、だんだんと自分の表現が始まっていく。はじめはただ拙いものに思えるのだけれど、男の子が、何を書いているのかわかりはじめると、これがもう。最初にさかのぼって、男の子が、なんとなく書いていたような言葉、ひとつひとつに、全部、深い意味があって、ちょっと背筋が冷めたくなるというか、涙腺が刺激され、たまらないことになります。多くは語るまい。ともかく、良い作品なので、是非、読んで欲しい一冊です。なんといういじらしさか。哀しいということが「哀しい」という言葉を使わずに表現されていること。そして、幼い心の健気さや、対象への慈しみが、深々と突き刺さります。はあああ、凄いなこれ。うっかり読むと読み過ごしてしまうところがあるので、じっくり読んでください。
さて、この物語の終わりに、実在の詩人、作家であるウォルター・ディーン マイヤーズが登場します。主人公の男の子の学校に、訪問授業みたいな形できてくれるのだけれど、これがなかなか良い場面です。作者のシャロン・クリーチが、ウォルター・ディーン マイヤーズの詩を読んで、思いついた物語であるがゆえ、の登場なのだけれど、なかなかない物語展開だと思います。ウォルター・ディーン マイヤーズといえば『ニューヨーク145番通り』の作者です。あの短編集も、とても詩的な雰囲気のある(とても良い)作品であったのだけれど、そうか、詩人でもあったのですね。実在の人物ではないけれど、少年と少女と、作家や詩人が交流する物語、は意外と多いですね(『ヘンショーさんへの手紙』、『お手紙レッスン』、『秘密の島のニム』など、これは手紙やメールでの交流モノ)。メアリー・フランシス・コーディの『旅路の果て』という作品は、作家モンゴメリーと、彼女の「最後の友人」となる少女との数日間の交流を描いたものですが、モンゴメリーほどになると、また意味が違ってくるような気もしますね。