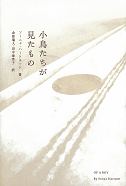 |
出 版 社: 河出書房新社 著 者: ソーニャ・ハートネット 発 行 年: 2006年12月 |
< 小鳥たちが見たもの 紹介と感想 >
子どもの頃に見ていた世界には色々なところにトラップがあって、迷い込んだら、恐ろしい異世界に運ばれてしまうような不吉な予感につきまとわれていました。地下世界へと降りていく、先が見えない雑居ビルの薄暗い階段。同じドアが無限に並んだ団地の長い屋内廊下。古いスーパーマーケットの事務所脇のトイレや、電気の消えたストック置き場。ご近所の魔窟の数々は地獄につながっている。恐怖をひきおこされるものが、いたるところにありました。しかも曾祖母が、数年前に起きた子どもの誘拐殺人事件の話を繰り返すものだから、びくびくしながら世界を生きていた気がするのです。あの薄暮時、本当に誘拐魔は暗躍していたのか。前フリが長くなりましたが、本書『小鳥たちが見たもの』は、そんな子ども時代のねじまがった世界認識と、異常なリアルとが混交して、不思議なハーモニーを生みだしている快作です。ハートネット作品は、どうにも感想を言葉にしにくいのですが、この作品の持つ味わいもまた玄妙で、この風味をどう表現したものか、と悩まされるところです。
1977年、日本の漁船が、全長10m程度の首長竜のような死体をニュージーランド沖でひきあげるという事件がありました。あれは、本当に恐竜の生き残りであったのか、それとも腐敗したウバザメの死体だったのか。この事件をニュースで見た当時の子どもたちは大きなインパクトを与えられました。それは東京にいた僕にも、この物語の主人公である、オーストラリアに住む少年、エイドリアンにとっても。海の怪物は本当に存在するのか。それとも、この世界には腐ったサメの死体しかないのか。エイドリアンの世界は、ひどく暗い不安に彩られています。父はおらず、精神を病んでいる母親とも別れて、祖母の家に引き取られ育てられているエイドリアン。祖母はエイドリアンの世話をすることにも倦み、それでもきびしい叱責は欠かさない人。同居している叔父のローリーは、自分が起こした交通事故で友人を植物人間にしてしまったことを悔いて、世界とのつながりを絶って引きこもっています。優しく、暖かとはいえない家庭生活。同じクラスの知的障害児、ホースガールは、一日中、馬のフリをして、奇声を上げ、多くの騒動を起こし、ある日、突然、いなくなってしまう。母親のように、自分もおかしくなってしまうのか。自分もまた、ホースガールのように消えてしまうのか。暗いリアル。友だちのほとんどいない学校。その頃、巷では、子どもたちの消失事件が人々を震撼させていました。近所に越してきた、あの三人姉弟は、本当は、誘拐されてきた子どもたちではないのか。唯一の友だちも、ある日、突然、手のひらを返してくる。祖母も叔父も自分を捨てようとしている。世界はリアルな恐怖に満ちている。エイドリアンの世界認識は、交錯していきます。海の怪物なんて本当はいない。この世界で、僕は、どう生きていったら良いのだろう。不安と孤独と恐怖。なにがあるわけでもなく、なにがないわけでもない。ただ、しっかりとうけとめてくれるものがないまま、不安に震える、子どもの所在のない心が、とても切ない悲しみを持った作品です。あの何もかもが大きく見えた、子ども時代の目線の先にあった、不思議な幻想に満ちて、それでいてリアルな世界がここにあります。幻想の先に、救いはあったのか。ともかく、なんとも凄い作品なのです。
そういえば、小学生の頃、各クラスに一人ぐらいは、「特殊学級」と「普通学級」の境界線にいる子がいて、この物語のホースガールほどではないものの、突然、奇声をあげたり、うろついたりするコントロール不能ぶりに戸惑わされていました。そういえば、あの子はいつ、同じクラスからいなくなったのだろう。担任の先生の顔を傘で突き刺しケガをさせたやんちゃな少年は、いつの間にか転校し、結局、公式アナウンスはないままでした。小学生の頃の記憶をたどると、はっきりとせず、ちゃんとした落しどころも不明で、なんら説明もないまま「終わってしまった」ことがらが数多くあります。まあ、世の中とはそんなものですよ、という教訓を無言のうちに与えられたのか。皆さん、そうなのだろうか。子ども時代の記憶に、あまり幸福な光が見えず、むしろ、薄暗い影ばかりが思い出されてしまう。友だちと遊んでいたことよりも、一人でとぼとぼと家に帰る姿ばかりが浮かんできてしまう。無事、大人になった僕は、だんだんと世界を包む幻想の薄皮が剥げて、むき出しの姿が見えるようになりました。過大評価も過小評価もしないで、世界を等身大で捉えられるようになったわけですが、少しはこの世界が安心できる場所になったのかも知れません。いろいろと懐かしい感情を想起させられる不思議な作品でした。