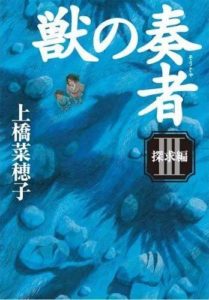 |
出 版 社: 講談社 著 者: 上橋菜穂子 発 行 年: 2009年08月 |
< 獣の奏者 第二部(探求編 完結編) 紹介と感想>
自分には「なさねばならぬことがある」という妄執。学者であるならば、そんな思いに「探究心」がたきつけられてしまうものでしょう。「この世を動かしている、見えない糸に連なる何か」が見えそうな時、その胸の疼きに身を委ねてしまう。それは知識欲という業(ごう)なのかも知れません。「知」と「理」のためには頓死しても、折り合いがついてしまうのが学者魂なのか。それこそが「天命」であるとの使命感がわきおこり、危ない領域にも踏み込みこんでしまう。この物語の主人公、獣の医師であるエリンにもこの傾向があります。まったくもって穏やかな家庭生活には向かない資質です。エリンの夫であるイアンも、武に一途な気質で、これまた守るべきもののためには命を投げだしがち。なんとも危険な夫婦だと思います。第一部から十一年が経って、エリンは結婚し、子どもも生まれました。十年間の束の間の幸福。しかし、時勢は再び切迫し、眠っていたエリンの使命感に拍車がかけられてしまいます。『獣の奏者』、第二部。やはり面白い。ぐいぐいと読ませる作品です。この世界の歴史に潜む謎。そして、紐解かれていく罪深い人間の性(さが)や業(ごう)。人間はどのように生きていく生き物なのか。究極的な真理に到達する過程を、エンタメ感たっぷりに読ませてしまう、そんな作品世界に脱帽します。この世界を知る、楽しむ、そして、考えさせられる。恐ろしいけれど、もっと知りたいという欲望がページを繰らせる。そして、その行為すら、考えさせられてしまう。そんな上質な読書時間を味わえる物語です。
降臨の野でエリンが王獣を操り、闘蛇軍を蹴散らしてから十一年が経過していました。闘蛇(その戦闘用モードである「牙」)がこの世界の強力兵器であることは変わりありませんが、闘蛇の天敵、王獣を、人間が意のままに操ることで、「牙」を超えた最終兵器になりうるという事実を見せつけた、あの闘いは衝撃的なものでした。王獣を操れる唯一の人間であるエリンは、軍事力の大きな鍵を握りながらも、一介の獣の医師として、策謀渦巻く危ういバランスの中を生き抜いてきました。かりそめの平和な日々を揺るがすことになったのは、かつてエリンの母が悲惨な死を迎えることになった原因でもある、闘蛇「牙」の大量死事件です。その事件の監察官として、大量死の起きた闘蛇村に派遣されたエリンは、定期的に発生しながら、これまで謎とされてきた「牙」の大量死の原因をついに究明してしまいます。それは、母が命を落としてまで隠そうとしていた秘密であり、闘蛇と王獣という、禁忌に守られていた二つの大いなる獣を自在に繁殖できる方法だったのです。やがて国と国との戦いが始まります。エリンはその職能をもって、真王に仕えながら、兵器としての王獣が孕む危険性をつきとめようとしてきました。獣の力を戦争に利用しようとする人間たちと、世界を滅ぼしかねない王獣の力。それを食い止められるのは自分しかいない。いつかくる破滅の時を先に見据えながら、エリンは自らとるべき進路をつき進んでいきます。やがて来るべき時がくる。その時、エリンは何を決断するのでしょうのか・・・。
「生き物の真の姿をゆがめようとする力にあらがう」、それを自分の使命だと思いながら、エリンは「獣たちには理性などない」こともわかっていました(ここがナウシカと設定の違うところです)。その大義自体、エリンが手前勝手に培ってきた妄念かも知れず、エリン自身もまた、それに気づいています。なのになぜ、エリンは進まざるをえないのか。自分の過酷な運命と等価の使命感を得てしまった不幸と恍惚。他者に頼らず、他者を巻き込まない生き方。そして、自分一人が命を捨てれば災いをくいとめられる、というエリンの覚悟。それはカッコ良すぎて、人間疎外の段階にまで進んでいます。実は人ひとり死んだところで何も変わりはしないのです。どんな重要人物でも、いないなりに世の中は回っていきます。悲運慷慨して憤死することだって自己満足に過ぎない。使命感と引き換えにする命。そんなのは美しすぎます。泥水をすすってでも、どんな場所でも、生き延びる道を探さなくては。真理に蓋をして見て見ぬふりをする。かりそめの平安の中に甘んじて暮らす。それもまた勇気です。使命感に殉死したい衝動を退けること。だって、子どもにとっては、代わりのいない、たった一人の母親なのですから。なのに、カッコ良い主人公であるエリンは、カッコ良く死地に赴きます。一人の英雄的な死さえ、闘いを止められるわけではない。その姿に衝撃を受け、興奮し、喜びと悲しみをないまぜにした感動に包まれてしまうのは我々、読者です。この圧巻のラストには打ちのめされます。是非ではなく、これはエリンという人間の生き方や心持ちを活写した物語です。それを我々は、ただ知るのです。もっと知りたいと願い、知ることで、人間は考えていく。物語が伝えるものを、体感できる、そんな読書体験がここには待っています。ふう。それにしても、理知と叡知の光に照らされるクレバーでキレすぎている作品です。禁忌や因習でさえも、ここでは合理主義の産物なのです。理不尽な掟も、土俗的な信仰もなく、道理が貫かれていきます。理知的に積み上げられた物語は、最終的にエリンを犠牲として、人智の愚かしさを現出するという理知を超えた不合理をやってのけますが、それを振り返り、考え、明日へとつなげていくのもまた人間の理知なのです。なんと理知的で「頭の良すぎる」物語。その魅力は充分にありますが、このファンタジーの地平にはもっと手に負えない魔物も潜んでいるような予感もあって、さらに読書の探求心を刺激されています。果たして、これまでの上橋作品はどうであったか、再検証したくなりました。これもまた知の欲求です。