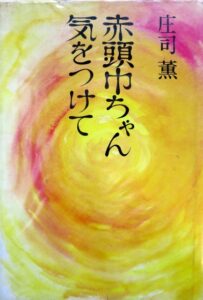 |
出 版 社: 中央公論社 著 者: 庄司薫 発 行 年: 1969年08月 |
< 赤頭巾ちゃん気をつけて 紹介と感想>
本書を最初に読んだのは、高校生の時、だったか、あるいは浪人生だったか。ともかく十代後半でした。シリーズ全部読みました。当時としても「古い本」でした。主人公はノンポリですが、カウンターには、いわゆる全共闘世代の学生気質が垣間見えて、軽佻浮薄な時代を生きていた遅れてきた世代である自分は、多少の憧れを持って眺めていました。同じく高橋和巳や柴田翔などの作品からも、その時代の匂いを感じていたと思います。現代(2024年)のYA層にとっては1960年代も1980年代も同じ昭和の、いわゆる「戦後」として認識されているのかも知れませんが、実際、かなり隔たりはあります。本書と同じ芥川賞受賞作の『至高聖所』は1980年代末の女子大学生の地味ライフが描かれていますが、そもそものバブル世相を踏まえないと、その作品の異色さや秀逸さが見えて来ません。そうした意味で、まずは1969年という時代感を押さえつつ、一方で、時代を越えた清新な表現や感性を味わいたいところです。1969年の1月。東大安田講堂が学生運動を行う全共闘の学生他によって占拠されたという事件は有名ですが、その時、受験生だった高校生は何を考えたか。受験が中止され、自分の将来について逡巡する中で、主人公の高校生男子、薫くんが学ぶことや生きることの本質を見つめ直していく、ライトな文体ながらも真を穿つ物語であり、その当時の世相や風俗描写が大いなる魅力でもあります。
物語は、東大法学部を志望する受験生である高校三年生の男子、庄司薫(かおる)が、安田講堂占拠事件によって入試が中止になったことで、進路に迷いながらも、自分の意志を決める一日を描き出します。この時、東大受験を目指していた受験生たちは、目標を喪失して仕方なく、京都大学や東工大に進路を変更せざる得なくなりました。周囲から同情を寄せられる存在となったことを、薫が面映く思うのは、最高峰の大学を受験できなくなったことを、エリートの悲劇としてステレオタイプで捉えられることです。薫が東大法学部を目指していたのは、人を幸せにするための勉強をしたかったからです。そんな本気を正面きって語ることもできないまま、周囲からはコースを外れてしまったかのように同情を寄せられることに薫は辟易してしまいます。ちょっとした事故で足の生爪をはがしてしまい、痛む足をひきづりながら、幼なじみの少女、由美を探して、自分の、受験をやめるという決意を打ち明けようとしている、薫が巡らせる物想いがユーモラスに語られていきます。一人、薫はさまよう町で、赤頭巾ちゃんのような幼い少女と出逢い、彼女のイノセンスに感化されます。優等生エリートの功利主義でもプライドでもなく、悪びれた気取りでもポーズでもなく、純然たる自分自身の気持ちに従う、小さな決意が輝くのです。
多分、自分が学生の頃だったら、サリンジャーの『エズメのために』あたりを引き合いに出して、友人にこの作品について語っていた気がするのです。実際、そんなことをしていたかも知れません。学生時代を思い出すと、そうしたカッコつけばかりが黒歴史として浮かんできます。ペダンティックやスノッブを冷笑して、真を穿つフリをしていたのも、しょうもないカッコつけで、実に恥ずかしいのです。好きな映画はフェリーニの『そして船はゆく』だと言っていました。それもまあ、ゴダールをあえてあげないような、良い塩梅を見計らっていたのです。ベタな流行映画をあげる勇気がなかったのは、自分自身への自信のなさの表れで、そんな微妙に高尚であるような趣味で身を守ろうとしていたのです。大したヤツではない自覚があったからですね。本書もまた当時の高校生気質、しかもエリート高の鼻持ちならない感覚が描かれます。それは優等生ぶること、ではなく、あえて優等生ぶらず、自分を貪欲に見せず、時には偽悪を装い、余裕のあるフリをして、興味本位に生きているフリをするカッコつけです。学生たちもまた政治的温度が高く、物事の是非を一刀両断しがちな風潮の中で、中庸でありつつ、ナメられないスタンスを保つにはポーズが必要だったのかもしれません。そんな世界の中で、自分の中のイノセントな渇望に応えるにはどうしたら良いか。本質を見極めようと、理想を追えば、少なからず社会的には損をします。悩まずにエリート路線を邁進すれば良いものを、と思うのは、持たざる自分のやっかみです。いずれにせよ学生って、どんな立場だろうと、いつの時代もそんなふうに自分のスタンスに悩むものだったんだよな、と過去の小説を読みつつ思っていた自分の学生時代も過去のものになりました。色々な情報や価値観にマルチにアクセスできるようになった現代(2024年)、学生さんたちにとって、どんな知識や趣味を持っているかということは、しかもそれをどう見せるかなんてことはどうでもいいことで、もはやアイデンティティはないのかもしれないのですが、かつて、悩みつつ本質を見極めていった学生たちの残像を物語で感じとってもらえると良いなと思います。