Eggs.
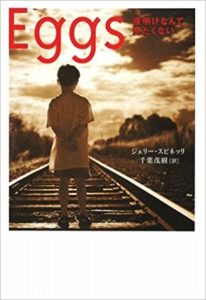 |
出 版 社: 理論社 著 者: ジェリー・スピネッリ 翻 訳 者: 千葉茂樹 発 行 年: 2009年07月 |
< Eggs 紹介と感想>
小学生時代に突然、親を亡くすと少なからず精神面に影響が及ぶ、というのが僕の経験則です。親のあっけない死によって、世界にはいたるところに穴が空いていて、すべり落ちるものなのだと教えられてしまう。世の中はすべて地雷原で、いつ自分や家族が闇の世界に連れていかれるかわからない。そんな終末感一杯の薄氷を踏むようなメンタリティで、小学生生活を明るく過ごすのは、やや難しいものがあります。昨今はメンタルケアがしっかりしていて、子ども心に歪みが生じても、上手くサポートとしてくれるものかも知れませんが、自分で乗り越えることには変わりがないでしょう。やがて迷走する気持ちを凍結して、前に進むのが得策だと悟るようになります。でも、未消化な気持ちは一時停止したままなのです。児童文学作品の中には、そうした気持ちのアーカイブを解凍させてしまうトリガーが沢山あります。この作品も、そうした意味でややしんどい読書となりますが、これこそが読みたいものだったりするので、まさに痛し痒しなのです。
清掃直後の濡れた床で足をすべらせて転んで頭を打ち、デイビットの母親は死にました。不運な、それでいてよくある事故。それで九歳のデイビットの世界はすっかり変わってしまいました。祖母の家に預けられ、父親には週末しか会えない。胸には、ぽっかりと穴が空いている。なぜか攻撃的になり、素直に祖母の言うことをきけないデイビット。自分がきちんとルールを守っていれば母親はきっと帰ってくる。そんな根拠のない期待から、誰にも知られぬよう秘かな規則を自分に課しています。ある時、デイビットはイースターの卵さがしの会場で十三歳の少女、プリムローズと出会います。プリムローズもまた、沢山の怒りや悲しみを内包した少女でした。占い師の母親はイカれていて、母親らしいことを何一つしてくれない。父親はおらず、往年の映画俳優、クラーク・ゲーブルの写真を自分の父親だと信じているらしいプリムローズ。二人は夜な夜なそっと家を抜けだして遊び歩きます。スーパーをうろついたり、フリーマーケットで売るものを集めたり、足の不自由な修理屋「冷蔵庫ジョン」の家でテレビを見たり。それほど仲が良いというわけでもなく、口喧嘩ばかりしている二人。時には、一切遠慮なしの悪口が、お互いの触れてはいけない一線を越えてしまうこともあります。それでも二人は一緒にいる。仔猫同士が噛みつきあったと思ったら、すぐに、くっついて丸くなって眠るみたいに。傷ついた子ども同士が寄り添いながら、疑似姉弟のような不思議な関係を築いていきます。感情をコントロールできないまま、怒りの衝動をもてあましているデイビットとプリムローズ。そんな二人を「冷蔵庫ジョン」をはじめとした優しい大人たちが見守っています。失望の夜を越え、希望の夜明けを迎えるには、越えなければならない障壁が沢山あります。いたるところに穴が空いた世界の中で、足をすべらせて穴に落ちそうになっている子どもたち。ずっと続く心の鈍痛に、特効薬のような「救い」があるはずはないけれど、失ったものの代わりに、大切なものを見つけだせることもあります。子どもたちの塞がった気持ちにシンクロさせられて、非常に苦しい読書ですが、彼らの輝ける「気づき」にもまた同調することができる感受性のドライブがここにあるのです。
『「スター★ガール」のベストセラー作家が贈る限りなく優しいストーリー』というコピーには含蓄があります。デイビットとプリムローズの関係性と、二人の周囲にいる大人たちの視線がこの物語の魅力ですが、そこには甘く優しい言葉はひとつもないのです。子どもながらに過酷な人生の洗礼を受けた二人は、上辺の言葉で結びつくことはありません。物語の後半、遠くフィラデルフィアを目指して、夜を徹して歩きながら、延々と続く二人だけの会話の場面がとてもいいんです。たわいもない会話を頼りに、二人は心を通わせていきます。『生卵と石と、ぶつけられるのならどっちがいい?』という質問をデイビットはプリムローズに投げかけます。怪我をしないだけ生卵の方がマシ、とはいえ、石の代わりに生卵をぶつけるのが優しさなのか。絶対的な「優しさ」について考えさせられます。子どもたちが「優しさに包まれている」と実感してくれたらいいのだけれど、大人の思惑どおりにはいかないものです。彼らが自分たちで、この世界から優しさを感じとっていくしかない。ささやかな旅の終わりに二人が見つけたものはなにか。読書による追体験は、もしかするとあの子ども時代に、自分が見つけていたものを、思い出させてくれるかも知れません。