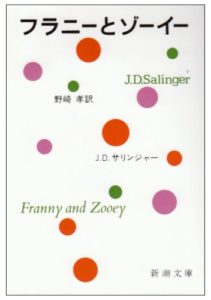 |
出 版 社: 新潮社 著 者: J・D・サリンジャー 翻 訳 者: 野崎孝 発 行 年: 1976年05月 |
< フラニーとゾーイー 紹介と感想 >
週末のボーイフレンドとのデートの最中に気を失ってしまった女学生のフラニー。彼女の精神状態は、極限まではりつめていました。彼女の繊細な神経は「大学」という場所が放つ、スノッブな空気に拒絶反応を起こし始めていたのです。教養を鼻にかけ、人を「こきおろす」ことで、自分の存在を大きくみせようとする優越感の権化のような学生たちに、吐き気をもよおすようになっていたフラニー。そして、今、レストランでの食事中に、自分の論文について滔々と論じ続けるボーイフレンドを前にして、相槌をうってあげることにも限界がきました。しかし、彼女もまた、学生という毒なる自分自身の腐臭を俄かに感じている一人。エゴや自己顕示欲の虜である、自分という存在にも辟易してしまっている。だから、他人の傍若無人な「尊大な魂」には、もはや耐えることができなくなってしまったのです。そんなフラニーの失意の週末を描いた短編『フラニー』と、彼女のすぐ上の兄ゾーイーが、彼女に人間としてのつながりを回復させることを試みる対話編こそが『ゾーイー』です。対をなす二編『フラニーとゾーイー』は、1950年代のアメリカの若者の自我を描いた物語です。サリンジャーの「グラース家の物語」の連作の中の二編で、この二作品だけで完結した世界を持ち、ひとつのテーマに貫かれています。他のグラース家の人々、特にこの7人兄弟姉妹の、賢すぎる長兄であるシーモアと次兄バディに幼い頃から影響を受け、「理性的」に育てられすぎた末弟のゾーイーと末妹のフラニーは、やや複雑な性格を形成されています。現在は俳優を職業としているゾーイー。彼は、鋼のような知性を身につけている青年であり、それゆえにギリギリの精神で生きています。辛辣さを身上としたその口ぶり。どんな物にも、定義を40は与えずにはいられないという、やっかいな自意識。自ら「僕は人とは話ができない、「解説」しかできないんだ」という、ごく普通のコミュニケーションを自由に行えない、悲しい知性の持ち主である彼。純粋な祈りのような真摯さに憧れながらも、皮肉な言葉を吐かなければなならない彼。そんな彼が、妹のために言葉を尽くして、「彼女のような(彼のような)人間」が生きていくすべを説いていく、そんな物語です。この兄妹の母であるものの、ごく普通の感性を持った「お母さん」の、良識ある一言が、ふいにゾーイーの胸に突き刺さりもします。ゾーイーも悟ったふりをしながらも、もがいている子どもなのですね。
結局のところ、他人のエゴや承認願望を揶揄したくなるのは、自分の中にある人間としての「いやらしい」部分を他人に見た時の拒絶反応なのだと思います。僕もまた学生の頃と比べると随分と足場が固まり、世界に対する適切な距離感がつかめるようになってきたのですが、この本のことを思うと、未だに疼くものがあるのは、若さというか、青さなのかも知れません(いい歳をして何を言っているか、です)。『フラニーとゾーイ』を初めて読んだのは、二十歳前後だったかと思うのですが、その当時は、まあ、リアルに突き刺さってくるものがありました。実に、鼻持ちならない尖った本なのです。自分たちを卑下しながら、優越感に浸っているような、そんな感じに思い当たることがありすぎて。それから何回か読み返してきたのですが、この作品に敏感に反応することから少し離れて、こうした「若者の懊悩」を傍観できるようになったかなあ。それは随分と幸せなことかなと思います。