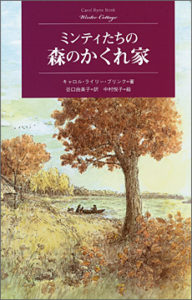 |
出 版 社: 文渓堂 著 者: キャロル・ライリー・ブリンク 翻 訳 者: 谷口由美子 発 行 年: 2011年01月 |
< ミンティたちの森のかくれ家 紹介と感想>
この作品がどんなに素敵かってことは、説明するよりも読んでもらうしかないのだけれど、ともかく手放しでお勧めできる一冊です。抒情的な風景の中でユーモラスな会話が交わされていく、真っ直ぐな心根の、とても愛おしい物語なのです。1968年に書かれた作品の本邦初翻訳。中村悦子さんの装画と挿絵が、あまりにも素敵に調和していて、見事に完成された一冊に仕上がっています。作者のキャロル・ライリー・ブリンクは、1936年に『風の子キャデイ』でニューベリー賞を受賞し、数多くの作品を書かれた後、1981年に亡くなられています。『大草原の小さな家』のワイルダーと同時代人という、もはや児童文学史上の存在ですが、その作品をこのような新刊という形で自分たちが読むことができる幸運を思います。毎年、過去の作品の初翻訳や、新訳での刊行が何冊かあるのが翻訳児童文学界(?)の良さで、古き良き時代のメンタテリティとストーリーを現在の日本語と編集で読めるのはありがたいものです(図書館の書庫に眠っている、過去の古い本をひっぱりだしてもらうのも、それはそれ秘密めいていて楽しいのですが)。ということで、この本は、関係者全方位に感謝したくなるような一冊でした。
1930年のアメリカ。世界恐慌の大不況の中、ミンティはパパと妹と三人で、シカゴからミネアポリスの伯母さんの家に移り住もうと車で向かっていました。パパに仕事がなくなってしまったからしかたがない、とはいえ、ミンティの気が重いのは、亡くなったママのお姉さんである伯母さんが、自分たちを歓迎していないのがわかっているからです。連れてくるなと言われているペットの犬だって一緒だし。そんなミンティの沈む気持ちに影響されたかのように、途中のウィスコンシン州で車が故障して動かなくなってしまいます。修理を呼ぶこともできないまま困っていたところ、ミンティたちは森の中に一軒の夏の別荘を見つけます。これから冬に向かおうという季節。夏の家、であるその家には、今は誰も住んでいないようです。一晩、お世話になろうと思い、その家に入ったミンティたちは、結果的にひと冬をその家で過ごすことになります。出ていく時にはお金を払おうと思いながら、ちょっと後ろめたい気分を抱えつつ、すごく素敵なその別荘で借り住まいをするうちに、周囲の豊かな自然の下、家族三人は次第に楽しい気持ちになってしまいます。お金はないけれど、家族がやたらと前向きで明るいのは、パパの性格のせいかも知れません。どんな仕事も長続きしない浮世離れしたパパと、そんなパパが大好きな娘二人。ミンティたちのひと冬の生活。ちょっとドキドキしたり、心配ごとはあるけれど、美しい自然の中、この素敵なかくれ家で過ごす日々は、なんだかやたらと輝いています。思わぬお客さんたちが登場して、ミステリアスな展開もありますが、登場人物たちの人間性の良さで、すべてが丸く収まってしまう。そんなハッピーづくしに、幸せな気分になれる一冊です。
所謂、ヤモメロマンです。母子家庭はリアリズムだけれど、父子家庭はロマンティシズムという物語の定石どおりです。更にお父さんがロマンチストで、長女がしっかりもので、妹はお茶目、となるとこの傾向は加速していきます。お父さんは色々な仕事に挑戦するものの、何をやっても上手くいきません。悪く言えば実務能力ゼロの人で、良く言えば詩人です。ワーズワースやブラウニングなど、多くの有名な詩人の詩を暗唱していて、詩になぞらえて物事を語ったりします。そして、最高に美味しいパンケーキを焼くことができる。それしか特技はないんだけれど、そんなパパを娘たちはスゴイと思っています。とはいえ、現実問題、お金の工面をしないとならないわけです。この家の借り賃だって、ちゃんと支払いたい。そこで、パパが挑んだのは「懸賞」です。広告文句を考えたり、短編小説を書いてみたり、賞金目当てにがんばるのですが、なかなか上手くいかない。もし、勝手にこの別荘を使っていることがバレたら、どうなってしまうのか。でも、これは絡み合った伏線が見事に収まり、心地よく着地させてくれる素敵な物語なのですから、読者は「安心」して、ミンティたちのことを「心配」していられるのです。なんといっても素敵なのは、この物語を貫く「つまらないことを、とびきりおもしろくして、それを一生懸命やることが、どんなに愉快か」というスピリットです。細かいところにも、良い場面が多くて、この家族の暮らしぶりを見ているだけで楽しくなってしまう。そんな幸福感に満ちあふれた物語なのですよ。良かったあ。