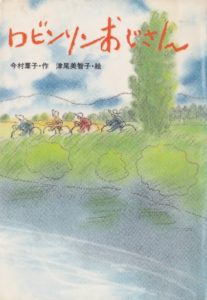 |
出 版 社: 講談社 著 者: 今村葦子 発 行 年: 1988年11月 |
< ロビンソンおじさん 紹介と感想>
今村葦子さんの高学年向け児童文学作品の魅力を上手く言い表す言葉をずっと探しています。この不思議な面白さはなんだろうなと考えているのですが、上手く説明することができないので、是非、作品を読んで欲しいのです。本書も、あるきっかけで六年生の女の子と、三年生の弟の心境が変化する物語です。大げさにいえば、世界観が変わります。ある日を境にこの世界の真理を知ってしまう、というほどのものではないのですが、目に見えていなかった繋がりが見えてきます。そのことで自分自身が深まっていくのです。これを「大人になる」という方向性での成長と捉えることもできるのですが、「大人」というニュアンスがまた微妙です。この物語には、主人公たち姉弟の叔父さんが登場します。お母さんの弟です。どうやら一流企業に勤めていたようなのですが、その仕事をきっぱりと辞めてしまうような「大人げない」人なのです。無論、そこには相応の慮りがあります。ただ、功利や安定を考えれば、分別に欠ける行為であって、大人的にはどうかと思われるところです。そんな叔父さんとの一緒に出かけた夏休みの冒険旅行で、姉弟は感化されてしまうわけですから、やや「大人」感が違うのです。処世術を学び、社会で上手くやることよりも、この世界の真理と向きあい、生きていく意味を考えていく、そんな大人になることもあります。成長のきっかけとなるトリガーが曖昧で、何か特別な痛みを伴うような出来事があったわけでもんくあ、それでも漠然と主人公に何かが下りてくるところが面白いのです。これまで読んだ今村葦子作品はいずれもそうだったのですが、この「啓示のようなもの」に心惹かれます。ある日、突然に世界は変わります。ちょっと長いのですが、本のあらすじを引用します。『北海道の小さな町に住む、とも子や浩たち家族のもとに、東京からぶらりと「おじさん」がたずねてきます。はじまりはただそれだけでした。でも、おじさんが去っていく日、とも子と浩のふたりは、もういままでのふたりではなかったのです。なにひとつかわらないのに、すべてがかわっていたのです』。なんと、この本の魅力が凝縮された見事なあらすじかと思います。これは、手にとらないではいられないでしょう。
北海道の小さな町に住む、とも子は小学六年生。両親と父方の祖母と二人の弟と暮らしています。せっかくの夏休みですが、小さなスーパーを年中無休で営んでいる両親は働きづめで、家族旅行に出かけることもできそうにありません。聞き分けのない三年生の弟の浩とまだ幼児の弟の相手をするだけの退屈な毎日。そんなところに、ふらりと、お母さんの弟である「おじさん」が訪ねてきます。半分ひげだらけの真っ黒な顔。いろいろな町を旅してきたというおじさんのお土産に子どもたちは歓びますが、実は東京で勤めていた「せっかくはいった、いい会社」を26歳の若さで辞めてしまっていたのです。「いくつになっても、ロビンソンの夢を見ている」と姉であるお母さんは、おじさんに激怒します。そでも、しばらくこの家に滞在することになったおじさんと、とも子たち姉弟は夏休みの毎日を過ごしていきます。ある日、浩と、とも子は家のすぐそばを流れている大川の源流を遡れないか、という話をはじめます。気持ちは盛り上がって、どんどんと冒険気分になってくる。最初は思いとどまらせようとしていた叔父さんも、いつの間にか覚悟を決めて引率することになり、さらにはお父さんまでついてくることになったのです。自転車に乗って、川の源流を遡る旅は、北海道の大自然に踏み込んでいく、壮大な冒険となります。山奥に暮らす人たちとの交流や、はじめての野宿、突然の豪雨に襲われることもあります。そんな自然の中で、おじさんやお父さんと交わす何気ない会話が、姉弟に大きな気づきを与え、目覚めさせていきます。なにひとつかわらないのに、すべてがかわっていく。子どもたちの世界観が覆される深遠な展開を、是非、見守っていてください。
『薔薇ノ木ニ 薔薇ノ花サク。 ナニゴトノ不思議ナケレド。 』といえば白秋です。この物語の主人公の、とも子が、驚きをもってこの世界の不思議に気づいていく姿には、どこか、この詩に通じるところがあるような気がします。おじさんとお母さんが育った遠い九州の田舎の家に、子どもの頃に書いた落書きが残されていたことを話し、そこにおじさんたち姉弟の子ども時代が残されたまま、今、自分たちがここにいることの不思議を、とも子に語ります。とも子は、また、おじさんとお母さんが、自分と弟のような姉弟であることや、お母さんのお父さんが亡くなった時のことなど、それまで意識してこなかったことを、突然に感じ入ってしまうのです。店番をしているお父さんと、家でテレビを見ているおばあさんが親子であることが、とても複雑でおもしろいことのように思えてきたり、おじさんに子どもが生まれたら、自分のいとことなるのだと、あらためて感じたり、ごくあたり前で、なんの不思議でもないことが不思議に思えて、どんどんと心が拡がっていくのです。あたり前の世界が、人と人とのつながりをもったとても大切なものに思えてくる。みんなが自分のそばに、確かな繋がりをもって存在していることに、どうしようもなく胸がはりさけそうになる。そんな気持ちの目覚めが情感豊かに描かれていきます。自分をすり減らしてまで会社員として働くことに疑問を持ち、仕事を辞めたおじさんの気持ちや、そのおじさんを羨んで、長男として家を継ぎ家業を続けざるを得なかったお父さんが漏らした言葉など、とも子が大人の心境に触れる場面も静かに響いてきます。子どもが考え深くなる、そんな季節が鮮やかに描かれる今村葦子作品の魅力を大いに感じられる一冊です。