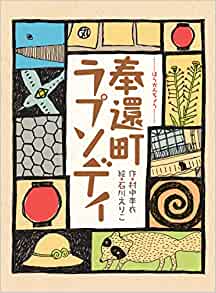 |
出 版 社: BL出版 著 者: 村中李衣 発 行 年: 2022年11月 |
< 奉還町ラプソディ 紹介と感想>
少年少女が賢明な老人と出会い、示唆を与えられる物語は児童文学の常套です。そうした老人たちは知恵があるだけではなく、どこか少年少女の魂を宿しています。親族である、おじいさんおばあさんではなく、全くの他人であり、少年少女と友情で結ばれる年長の友人となる、ボーイミーツオールドボーイや、またその逆パターンには傑作が多いものです。お互いの重なる時間はあらかじめ短く、遠からずお別れの予感を孕んでいることも、この関係性の魅力かも知れません。この物語もまた少年たちが老人と出会う物語なのですが、そうしたお話とは方向性が違っていて、それでいて魅力的なのです。なによりも老人たちの「ちょっとヤバい感じ」に妙味があります。ややボケはじめたお年寄りと子どもの関係性を描く物語もまた児童文学には多く、介護の苦闘をこえて、その老化を鷹揚に受け止めていく姿が描かれますが、本書は、そのパターンともちょっと違います。非常に危うい老人たちが何人も登場します。妄想や妄言もあり、手に負えない制御不能な人たちです。少年たちは、こうした老人たちをどんな眼差しで見つめていたのか。可哀相と思う気持ちなど微塵もなく、そのパワフルでファンキーな姿に畏敬の念を抱いている感じがグッときます。それでもどこかに哀しみはあります。それさえも笑いとばせるような、なんだかカッコいい異次元に連れていかれる。これぞ読みたかった村中季江さんの物語なのです。
幕末の大政奉還の際に大名に配られた奉還金をもとに始まったと言われる歴史ある商店街。それが奉還町商店街です。さびれたとはいえ、店主たちもまた今もって、ちょっとやそっとじゃ「負けられない」誇り高さがあります。中でも古い洋品店で、いつも何体ものマネキンに囲まれて黙って空を見上げている「べにや」のおっちゃんは、さとしやあつしのような子どもたちからもおっかない人だと恐れられていました。商店街にテコ入れしようとテレビの取材があった時だって、レポーターをこわい顔でにらむだけ。そんなおっちゃんが入院して、「たねやのノダ」のおばあちゃんに頼まれた、さとしたちはお見舞いにいくことになります。そこで二人はおっちゃんから、いつも空を見上げているワケを聞くことになりますが、これがなんとも飛んだ話なのです。子どもたちは商店街の老人たちと交流しながら、ちょっと不思議な体験をします。老人たちは迷妄しつつもバイタリティにあふれていて、子どもたちも圧倒されてしまうのです。亡くなった旦那さんが博多で買ってきてくれた明太子が食べたいと言う雑貨屋のナミばあを連れて、岡山から新幹線に乗った、さとしとあつしの旅。元気を無くしていたナミばあを励まそうとする二人が、なんだか切ない気持ちになってしまったのはなぜか。ちょっとボケてしまっているけれど、天真爛漫なお年寄りたちの姿と、それを見守る子どもたちの間合いがなんとも言えない空気感を醸し出す愛おしい物語です。
読み終えて、あらためて「奉還町ラプソディ」というタイトルの絶妙さに感じ入っていました。哀愁のある「ブルース」ではなく、自由奔放な狂詩曲「ラプソディ」なのです。危うさがそこかしこ見え隠れしています。奔放すぎて手に負えない感もあります。老人たちは、制御が効かなくなりつつある状態です。とはいえ、心はどこまでも自由であり、そんなパワーで少年たちがひれ伏すようなムーブを起こし続けて欲しいと思うのです。認知症や痴呆症の人との付き合い方として、深刻になりすぎないことが重要だろうと思っています。無論、心配だし、心労は多いでしょう。同じ会話を何度も繰り返されると泣きたくなってくるのは、以前の明晰だった頃を覚えているからです。その衰えに、哀しみを感じてしまうものです。祖母が次第に認知症の症状を現しはじめた時、あまり気にしないようにするというスタンスでいました。気にしなければ、気にならないかと言われるとそんなことはありません。そんな状態の祖母と暮らした時間は長くはなかったので、また考えてしまうところもあります。本書には『満州むすめ』という歌が登場します。かつて満州で育ったという、ノダのばあちゃんのお母さんのみつさんが口づさむ歌で、子どもたちには無論、なんのことやらなのですが、ここに長い人生の轍が垣間見えます。満州で暮らしたことのある自分の祖母もこの歌を口にしていた記憶があり(完全に記憶の彼方にあったものと再会させられて驚いています)、ちょっと切なくなりました。この歌を覚えている人がまだどこかにいると思うと(やや差別的なニュアンスもあり道義的にはともかく)、それでも嬉しくなります。もはや消えていくべきものかも知れないものですが、ここに繋ぎ止められていることで、また会いにいける、そんな気がしています。