Tagebuch von Ryo
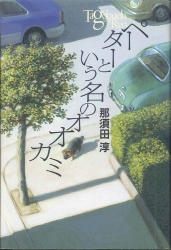 |
出 版 社: 小峰書店 著 者: 那須田淳 発 行 年: 2003年12月 |
< ペーターという名のオオカミ 紹介と感想 >
新聞社駐在員の息子である日本人少年リオと、世界的音楽家を父に持つ日独ハーフの少年アキラ。親の都合で、せっかく住み馴れたドイツを離れることになったリオと、両親の離婚で横浜から引っ越してきたアキラが、ドイツで出会ったのは、ほんの偶然のことでした。まだ自分の力で自分の居場所を決めることができない少年たちは、それぞれ親への不満と、自分が省みられないことに寂しさを覚えています。そんな時、野生動物研究所からオオカミの群れが逃げ出すという事件が持ち上がります。オオカミには懸賞金がかけられているという話を聞いて、少年たちはにわかに興味を持ち始めます。リオの友だのフランチェスカの大叔父さん、マックスがここ数日、飼い始めた犬、ペーター。リオたちはこの犬が、現在逃走中の群れからはぐれた子オオカミなのではないかと疑いを持ちます。しかし、オオカミをつかまえるために、その生態を調べはじめた少年たちは、野生オオカミの真実を知り、だんだんと野生で生きることこそが彼らにとって幸せなのだと感じるようになります。果たして、ペーターのために動きはじめた少年たちとマックスが、オオカミの群れを追って、たどりついた場所は旧東ドイツ領。東西対立の象徴だった、ベルリンの壁は、リオやアキラが生まれる前に取り壊され、すでに「歴史」の一部になっていました。しかし、それぞれの壁の中に閉じ込められていた人間たちの痛みは、未だに癒えることなく疼いていたのです。
マックスは、無愛想でとっつきにくい人物でした。心に影のようなものを抱いている寡黙な男性です。マックスはその少年時代、ある事情で親のいる西ドイツに帰れなくなり、親族に引き取られ、東ドイツの国民として成長しました。党による専制、密告、裏切り、キナ臭いものが渦巻く旧東ドイツで、いわれなき差別を受け、心を傷つけられて育ったマックス。少年たちは、ボーズ・ミーツ・オールドボーイの常套どおりに、この気難しい男性と心を通わせていくことになります。かつてマックスは、大切にしていた人を守るために、友人を裏切り、国に売ったことで、その名誉を失っていました。マックスの過去を知った日本人少年二人は勇気を奮いおこし、ちょっとしたアクションを試みます。少年たちがいなくなったことが、誘拐騒動に発展したり、オオカミを危険視する世論がまきおこるさなか、リオの作ったお父さんへのビデオレターが功を奏して、事態は急展開していきます。果たして、少年たちはこの冒険をうまくやり遂げることができるのでしょうか。
父と息子の関係性について、この物語の中で強く印象づけられるところがあります。少年たちにとって、父親はやはり特別な存在です。父親という「壁」は、かならずしも越えなければならない邪魔な障壁、というわけではありません。はっきりと愛情を口にするわけではないけれど、実は、父親が「ちょっと背中を押してくれていた」ことに少年は気づいているものです。悔しいけれど、認めなくてはならない。どっしりとした、大きくて暖かい壁のように自分を守ってくれている存在感を、最後に少年が感じるあたりに、この作品の妙味があったかと思います。自分は、はぐれものの一匹オオカミではなく、両親や、孤独をシェアできる友人たちがいる。マックスの悲しみを知った少年たちは、マックスやペーターのために、彼らができることをやろうとします。少年たちがふと大人びる「成長」の瞬間。そして中高年が一瞬、少年を取り戻すあたりに、爽やかな印象を与えられる作品でした。作者の那須田淳さんと言えば、作家であるのみならず、ミヒャエル・ゾーヴァ作品の翻訳者としても知られていますが、児童文学ファンにとっては、やはり児童文学者である那須田稔さんのご子息だということも大きいですね。父と息子の関係性なんて当事者としては面映ゆいものだと思いますが、(池澤夏樹作品に福永武彦の面影を探すように)どこかロマンを感じさせるものがあるものです。同じく那須田淳さんの『一億百万光年先に住むウサギ』もまた、父親と子どもの愛情の形を、さりげなく見せてくれる優れた作品でした。元気を失っていた父親が力を取り戻すとき、少年もまた勇気づけられる。親の世代が若い頃に経験した恋愛や心のドラマに思いをはせながら、これから全てをはじめようとしている中学生の少年少女たちの視線が清々しいのです。国内を舞台にしたものでも、どこか洗練された翻訳児童文学のような感覚があるのも那須田淳作品の魅力です。