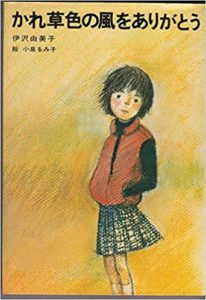 |
出 版 社: 講談社 著 者: 伊沢由美子 発 行 年: 1981年12月 |
< かれ草色の風をありがとう 紹介と感想 >
花里団地の裏には埋めたて地があり、広大な干潟が拡がっています。干潟に群れをなしている飼い主から捨てられた犬たちは危険視されていたけれど、二年生の集にとっては大切な友だちでした。ここには多くの野鳥も現れるため、野鳥の観察会に参加する子どもたちが野犬に襲われることを憂慮した保護団体が、捕獲作戦を敢行し、犬たちを捕えて保健所に送りました。集は捕らえられた犬たちを救い出すために、知りあいの上級生の克とサチに協力してもらい、夜、保健所に忍び込みます。でも、そこで集が見たものは、既に薬殺された犬たちの死骸でした。干潟で足を怪我したコチドリの世話をしている少年、克は、鳥を襲う犬たちをわずらわしく思っていたけれど、野犬が無残に殺されてしまったことに怒りを覚えます。それでいて、害虫を殺し、動物の命を食べて生きている自分自身をどう考えたらいいのかわからなくなってしまいます。一方、団地に暮らす少女、サチは両親の離婚問題に揺れていました。父親は家を出ていってしまい、母親との二人の生活。父親方のおばあちゃんにも会えなくなったことが寂しくて、父親と一緒に暮らしているおばあちゃんの家をふいに訪ね、そこにオシメが干してあることをサチは目撃してしまいます。父が再婚していたことを知らされていなかったサチは、自分が見たものに驚き、ただ戸惑うのです。サンケイ児童出版文化賞他、多数の賞を受賞した伊沢由美子さんの代表作である本書は「動物の殺処分」と「両親の離婚」という子どもの心に重く響く題材を扱っています。あまりの鬱展開に気持ちが暗くなるのですが、そこをひとつ堪えて、読み進めて欲しい実りのある作品です。
子どもたちが呆然と立ち尽くす姿を見せつけられる作品です。この物語には甘い救済は用意されていません。子どもたちは現実の壁に当たって、それをただ呑みこむしかないのです。大人は子どもたちの心を救うこともしないし、おためごかしさえも言わない。それでも子どもたちは、この世界に失望せずに歩き出します。そこには、ただ子どもたちのいたわしい自助の姿があります。克が世話をしていた、ケガで片脚を失ったコチドリは、物語の終盤、再び空へと飛びたちます。コチドリを空に舞わせた「風」にサチは見覚えがありました。それは、自分たち家族が幸せだった、あの日から吹いてくる「かれ草色の風」だとサチは思います。『かれ草色の風をありがとう』というタイトルは、物語の終わりにサチから父親にあてて送られた手紙の中の言葉です。自分と母親を捨てて、新しい家庭を作って出ていってしまった父親に寄せる言葉としては健気すぎて、困ってしまうほどです。幸せな時間を作ってくれたことを父親に感謝し、今度は自分でその風を吹かせようと考えるサチ。いつかその風は、傷ついたサチを再び空に舞いあがらせることになるのかも知れません。見事な成長の物語ではあるのですが、現代の視点で読むと、複雑に感じてしまうことや、これでいいのかと考えさせられるところも多い作品ですね。
自分自身も体感したことですが、この頃はまだ、子どもがショッキングなことに遭遇しても、メンタルケアを施すことが浸透していない時代でした。大人から「同情」されることはあっても、心の問題を吐露したり、正しく支援してもらえる場はありません。これは「子どもの心をケアする制度や環境が未発達な世界」のお話ですが、同時代にその問題点が意識されるものではなかったと思います。だからこそ、傷つく子どもたちの鋭敏な感性や、克己心を描けたのかも知れないし、子どもの心に寄り添うこうした物語に支えられた子どもたちもいたのではないかと想像しています。サチが「両親の離婚」に真正面から傷つけられる姿も注目すべきところです。かろうじて受け身がとれたとはいえ、かなりハードなパトスです。児童文学が描く「両親の離婚」という題材は、もう十年も経つと、普通の家族に起こりうる当たり前の出来事として物語に溶け込んでいくし、両親が離婚することを明るくユーモアを交えて描き、繊細な心の動きを逆照射する方がスタンダードとなっていきますが、本作の両親の離婚はただただショッキングであり、そこから再起することも容易ではありません。これはポストモダンとして復権すべき純粋で魅力的な感性表現なのではないかと考えます。目も当てられない痛ましい喪失感があります。その痛みを力に変えていく気持ちの強さもまた存在します。幸福だった過去から吹いてくる「かれ草色の風」という概念は抽象的ですが、その風を自分で吹かせようという決意を少女がみなぎらせることには、心を動かされずにはいられないのです。ただ、まあ、かなり参りますね。かなり。しばし、うなだれます。