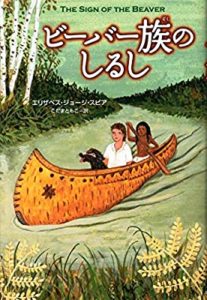 |
出 版 社: あすなろ書房 著 者: エリザベス・ジョージ・スピア 翻 訳 者: こだまともこ 発 行 年: 2009年02月 |
< ビーバー族のしるし 紹介と感想>
1768年、アメリカ。マサチューセッツに住む白人家族が、より北東のメイン地方に買った土地に入植しようと計画していました。まだ白人が入り込んでいない場所を開拓して住もうという挑戦です。まずは先行して、父親と十二歳になる息子のマットがこの土地にはいり、丸太小屋を建てました。準備が整ったので、今度は母親とマットの妹を迎えに、父親はマサチューセッツに戻ることになります。マットをこの森の丸太小屋に残し、六週間で戻ると言って出かけた父親。マットは不安を抱えながらも、一人、ここで家を守っていました。ところが、行きずりの男に父親から託されたライフル銃を盗まれ、熊に食糧庫を荒らされて、食べ物を獲ることもできないまま窮地に陥ります。魚を釣っても、塩さえなく味気ない。味覚に飢えて蜂蜜をとろうとして、ミツバチに刺されて、池に飛び込み意識を失いかけたところを、マットはインディアンの老人に助けられます。フランス軍と結んだインディアンたちが、イギリス軍に敗れて終わった戦争以降、この辺ではほとんど姿を消し、関わることはないと思っていたインディアンに助けられて、マットは驚きます。彼の窮状を知っていたインディアンの老人サクニスから、マットはひとつの提案を受けます。食べ物を供給する代わりに、サクニスの孫である少年、エイティアンに文字を教えて欲しいともちかけられたのです。こうして、同い年の少年二人が、その立場や人種を越えて向かい合う物語が始まります。これがまたツボに入りまくりの、当初は反発し合う少年同士が次第に理解を深めていく、あの魅惑的な物語空間が展開されていきます。しかし、入植者である白人とインディアン(ネイティブアメリカン)の関係はいたって難しいものです。そうした厳しい現実を知ることも含めて、少年が成長していく姿を見守ることのできる物語です。
サクニスは白人に不利な契約書を結ばされているインディアンのためには、自分たちも文字を習得する必要があると考えていました。一方で文字を覚えさせられる孫のエイティアンとしては不服があります。狩人になることが目標であるエイティアンとしては、この白人少年に文字を習うことに納得がいかないのです。マイクもまた、そんなエイティアンにどうやって文字を教えたら良いのか悩みます。そこで手元にある唯一の物語であった『ロビンソン・クルーソー』を使って、エイティアンの関心を引こうと考えます。とはいえ、これもなかなか難しい。面白いところを読みつなぎながら、少しずつエイティアンが興味を向けてきてことにマットは手応えを感じます。マットはエイティアンに狩りや罠の仕掛けを教えてもらい、次第にこの自然生活のコツを掴んでいきます。森の中で一緒に行動するうちに、エイティアンたちビーバー族のしるしがつけられた場所を教わり、彼らの土地に関する考え方を知ることにもなります。白人とインディアン、その考え方の違いは色々なところに現れ、マットはエイティアンと言い争うこともあります。『ロビンソン・クルーソー』を楽しみながらも、原住民である従者フライデーとクルーソーの関係に、エイティアンが腹を立てることも、マットにはわかるようになっていきます。自然生活に不慣れことを冷笑するかのようなエイティアンに、たまに認められることにマットが嬉しくなってしまったり、いつか自分がピンチのエイティアンを助けだすことを夢想したりと、その関係性は次第に変化していきます。しかし、エイティアンの村に招かれたマットは、彼の両親が白人に殺されていることや、他の村人たちがマットに対して良い感情を持っていなことも知ってしまいます。それでも、マットがエイティアンのためにとった行動がインディアンたちの心を動かし、マットは仲間として認められていくようになります。春に旅立ったマットの父親は帰ってこないまま時間は経過していき、やがてこの地域にも冬が訪れようとしていました。村ごと狩場を移動しようとするインディアンたちと共に、この土地を離れないかとマットは誘われます。さて、その時、マットはどう決断したのか。インディアンたちとの交友の中で考えを深めていったマットの成長が頼もしくも羨ましく感じられます。
物語の最大の魅力は、やはり、ぶっきらぼうでツンケンとしたエイティアンと、マットの関係性です。最初は互いに反発しあっていた二人でしたが、感情を表に出さないエイティアンに、ちょっとした喜色を見出して、マットが嬉しくなったりするのも、なんだか楽しいところです。実はエイティアンが、マットから聞き覚えた『ロビンソン・クルーソー』の物語を、帰ってから妹に語って聞かせていた、なんてことをマットが後から知るあたりも良い場面で、仏頂面したエイティアンの心の裡にマットが触れていくあたりはどうにも微笑ましいのです。『ロビンソン・クルーソー』の物語を読み終えたマットが、今度は旧約聖書の話をすると、エイティアンからもインディアンの同じような言い伝えを聞かされ、その豊かな文化を知ることにもなります。大人の狩人として次のステージに進もうとしているエイティアンとの距離に、少し寂しさを感じてしまったりと、そんなマットの心の動きも清新で、文化や考え方の違いを越えて、人と人が心を交わし、絆が生まれていく姿がさわやかに描かれている物語です。1984年のニューベリー賞オナー受賞作で、その当時、翻訳も刊行されている本ですが、新訳刊行であらためて、その魅力を伝えてくれた一冊です。少年たちの友情ものが好きな方も、また『青いイルカの島』や『ひとりぼっちの不時着』のように、大自然の中を一人で生きぬく子どもの話が好きな方も、きっとワクワク、ドキドキさせられること請け合いです。